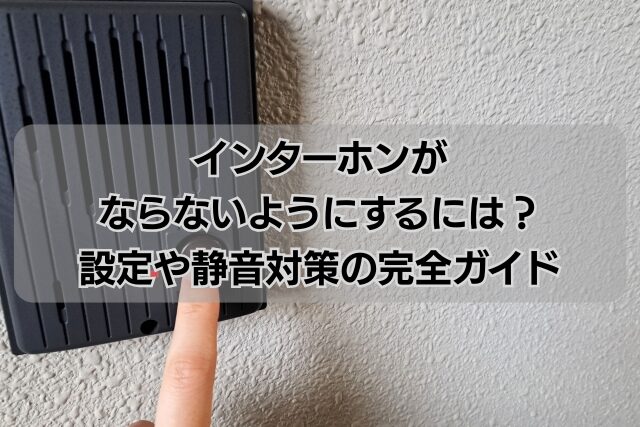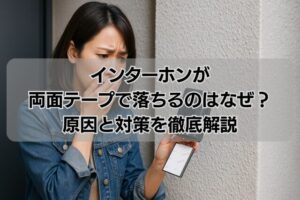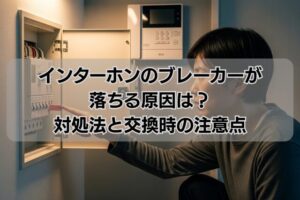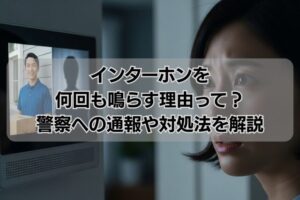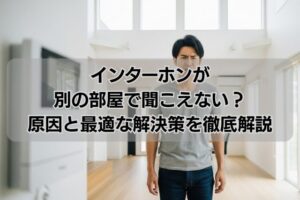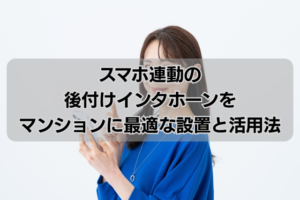赤ちゃんの昼寝中や在宅ワーク中など、できるだけ静かに過ごしたい時間に「ピンポン…」と鳴るインターホンの音に、悩まされていませんか?この記事では、インターホンがならないようにするための、具体的な方法をまとめています。
まずは、インターホンの音を消す方法として、音量の設定変更や消音機能の活用、またはインターホンの電源を切る方法など、機種別の対応策をご紹介します。また、受話器を外しておけばインタホーンは鳴らないのかという疑問に対しても、機種ごとの違いやリスクについて解説します。
さらに、音量設定を変更する際の注意点や、インターホンが消音機能付きでない時の対処法についても詳しく触れています。自宅の機種に消音設定がなければ、物理的に音を抑える工夫や、インターホン押さないでステッカーを貼るなど、補助的手段も検討が必要です。
また、インターホンが勝手に鳴ってしまう原因とは何か、誤作動への対応方法なども取り上げます。もしインターホンの買い替えを検討しているなら、消音機能付きインターホンの費用相場や、おすすめの商品情報も役立つでしょう。
 ジロー
ジローもう「鳴らないでほしい…」とイライラしないために、あなたにぴったりの方法を見つけてください。
【記事のポイント】
1.インターホンの音を消す、具体的な方法がわかる
2.機種別の電源の切り方や、注意点を理解できる
3.消音機能がない場合の、対処法を知ることができる
4.音が鳴る原因や、交換すべき機種が判断できる
インターホンがならないようにするガイドと注意点


- インターホンの音を消す方法
- インターホンの電源を切る方法
- 受話器を外しておけばインタホーンは鳴らない?
- 音量設定を変更する際の注意点
- インターホンが消音機能付きでない時の対処法
インターホンの音を消す方法


インターホンの音を消すには、まずお使いの機種に合わせた方法を選ぶ必要があります。多くのインターホンには音量を調整したり、完全にミュートにする機能が備わっており、それを使えば簡単にチャイム音を消すことができます。
呼び出し音量設定の変更
一般的な対処法としては、呼び出し音量設定を変更する方法があります。設定画面にアクセスし、「呼出音量」「チャイム音量」などの項目を探し、「小」「切(ミュート)」を選択してください。Panasonicやアイホンといった大手メーカーの機種には、比較的わかりやすい画面で操作が可能です。
音量つまみや消音スイッチの確認
もしメニュー画面がない古い機種や、ボタン操作に不慣れな方であれば、機器の側面や背面にある物理的な「音量つまみ」」消音スイッチ」を、確認するのも一つの方法です。このつまみを最小にすれば、音をほとんど出さずに使用できます。
ただし、音を完全に消してしまうと、宅配業者や来客に気づけないといった不便もあります。特に一人暮らしの方や、日中在宅している方にとっては、応答の遅れがトラブルの原因になる可能性もあります。
デメリットを補うための方法
こうしたデメリットを補うには、「音は消すが光で来客を知らせるタイプ」「外部チャイムを別の部屋に設置する」などの方法を、検討してみるのも良いでしょう。インターホンの設定や仕組みは機種によって異なりますので、まずは取扱説明書を確認することをおすすめします。
なお、音量調整や消音設定が見つからない場合は、物理的にスピーカーをジェルマットなどで覆う方法も有効です。



ホームセンターや100円ショップで手に入る耐震ジェルを使えば、跡を残さず手軽にチャイム音を抑えることが可能です。
インターホンの電源を切る方法
インターホンの音を完全に止めたい場合、電源を切るという手段もあります。ただし、どのような方法で電源を切れるかは、インターホンの電源方式によって異なります。無理に操作すると故障や感電の危険もあるため、正しい知識が必要です。
電源種類の確認
まず、インターホンの電源は主に3種類あります。コンセントに挿す「電源コード式」、乾電池で動く「電池式」、そして壁の中の配線から電源を取る「電源直結式」です。
1.電源コード式の場合
電源コード式の場合は、親機の電源コードをコンセントから抜けばすぐに電源を切れます。これは最も手軽で安全な方法です。
2.乾電池式の場合
乾電池式であれば、電池ボックスのふたを開けて電池を抜くことで音を止められます。玄関チャイムなどの簡易型インターホンでよく採用されている方式です。
3.電源直結式の場合
問題は電源直結式の場合です。このタイプは壁の内部にある配線から電力を供給されており、素人が勝手に外すことはできません。誤って触ると感電する恐れがあるほか、建物の配線に影響を与える可能性もあります。
このため、電源直結式のインターホンの電源を切りたいときは、ブレーカーを一時的に落とすか、専門の業者に相談する必要があります。
ただし、ブレーカーを切るとインターホンだけでなく他の家電も使えなくなるため、生活に支障が出る場合があります。賃貸住宅ではブレーカー操作が禁止されていることもあるため、まず管理会社や大家さんに相談してください。
このように、インターホンの電源を切る方法はタイプによって大きく異なります。



安全性や住環境への影響を考慮して、最適な方法を選ぶことが大切です。
受話器を外しておけばインタホーンは鳴らない?


インターホンのタイプによっては、受話器を外しておくだけで呼び出し音が鳴らなくなる場合があります。ただし、すべての機種で有効な方法ではないため、事前に確認が必要です。
オートロック付きの集合住宅などに多い「受話器型インターホン」は、受話器を上げたままの状態にしておくことで着信音が鳴らなくなる設計のものがあります。電話機と同じ仕組みで、通話状態を常に維持することで着信信号を遮断する仕組みです。
この場合、ピンポンという呼び出し音が鳴らず、代わりに相手が「応答なし」と認識するようになっています。
ただし、機種によっては受話器を外しても音が鳴るものもあり、確実な方法とは言えません。また、受話器を外したままにしておくことで、内部のスピーカーや回路に常時通電状態が続き、故障や誤作動の原因になる可能性もあります。
さらに、住人不在と誤解されるリスクもあります。たとえば空き巣が在宅かどうかを確認するためにインターホンを押すことがありますが、反応がないと留守だと判断されてしまう可能性もあります。
このように、受話器を外す方法は一部の機種では有効である一方、リスクやデメリットも伴います。



もし確実に音を止めたい場合は、設定画面からの消音操作や、消音機能付きインターホンへの交換など、より安全で安定した対処法を検討するほうが安心です。
音量設定を変更する際の注意点
インターホンの音量を変更することで、騒音の軽減や静かな環境の確保が可能になります。ただし、設定を変更する際にはいくつかの注意点があります。操作ミスや設定忘れによって、来客に気づけず不便を感じるケースも少なくありません。
1.変更した音量の状態が目視できるかどうか
まず確認すべきなのは、「変更した音量の状態が目視できるかどうか」です。機種によっては、現在の音量が画面上に表示されず、どのレベルになっているのか分かりにくい場合があります。とくに「消音(ミュート)」設定にしていることを忘れ、そのまま来客に気づけなかったという失敗はよく起こります。
2.保存される設定かどうか
また、音量設定の変更は一時的な操作ではなく、「保存される設定」かどうかも重要です。一部の機種では、電源を切ったり再起動したりすると、音量が初期設定に戻ってしまうことがあります。使用しているインターホンの取扱説明書を事前に確認し、設定が維持される仕組みかどうかを把握しておきましょう。
3.音を小さくし過ぎたことによるデメリット
もう一つのポイントは、音を小さくしすぎたことで「実際には鳴っているが、本人が気づかない」という状況になることです。これは高齢者や聴覚に不安のある方がいるご家庭で特に注意すべき点です。設定後は一度テストして、実際に聞こえるかを確認するのが確実です。
4.無理な操作は故障の原因に…
最後に、設定操作自体がやや複雑な機種もあるため、無理に操作を進めると「故障の原因」になることもあります。不安がある場合は、メーカーのサポートや販売店への問い合わせも視野に入れてください。
このように、音量設定の変更は簡単そうに見えて意外な落とし穴があります。



静かに過ごしたい気持ちを優先しつつも、生活に支障が出ないバランスを見極めて設定することが大切です。
インターホンが消音機能付きでない時の対処法


消音機能が付いていないインターホンでも、いくつかの工夫でチャイム音を抑えることは可能です。機種の機能に頼らず、物理的な対処や周辺環境の工夫によって、音を軽減する方法があります。
振動を吸収する素材を貼る
まず試したいのが、スピーカー部分に「振動を吸収する素材を貼る」方法です。おすすめは耐震用のジェルマットで、ホームセンターや100円ショップで手軽に入手できます。ジェルの柔らかさが音の振動を吸収し、チャイム音をかなり小さくできます。
貼る位置は、音が出る穴の真上を中心に、横にも広く貼るのが効果的です。貼って剥がせるタイプなら、賃貸住宅でも跡を残さず使用できるため安心です。
インターホン全体を布で覆う
また、スピーカーの構造が分かりにくい場合には、「インターホン全体を布で覆う」方法もあります。この方法は見た目に多少の違和感が出ますが、素材によっては音を吸収し、実用面では効果的です。テープで固定すると跡が残る可能性があるため、結束バンドなどを使って優しく固定すると良いでしょう。
完全に無音にしたい場合は交換
一方で、これらの方法はあくまで音を小さくするものであって、「完全に消す」ことは難しいという点に、注意が必要です。完全に無音にしたい場合は、新しいインターホンへの交換や、音を光に変えて知らせるワイヤレスチャイムの導入なども検討するとよいでしょう。
特に、オーム電機やパナソニックのワイヤレスチャイムは、光のみで来客を知らせる設定が可能な機種もあります。
なお、こうしたDIY対策が難しい場合や効果が不十分な場合は、専門業者への相談も選択肢となります。特に壁内部の配線が関係しているケースでは、資格を持った技術者に依頼することで安全かつ確実な処置が可能です。
このように、消音機能がないインターホンでも工夫次第で対応可能です。



ライフスタイルや住宅環境に合わせて、無理のない方法を選ぶことが大切です。
インターホンがならないようにするための選択肢
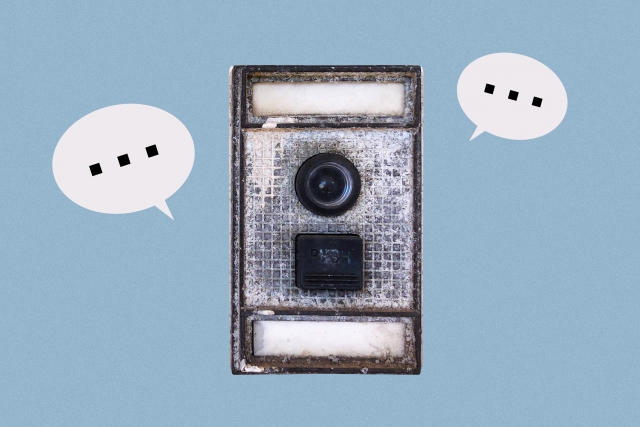
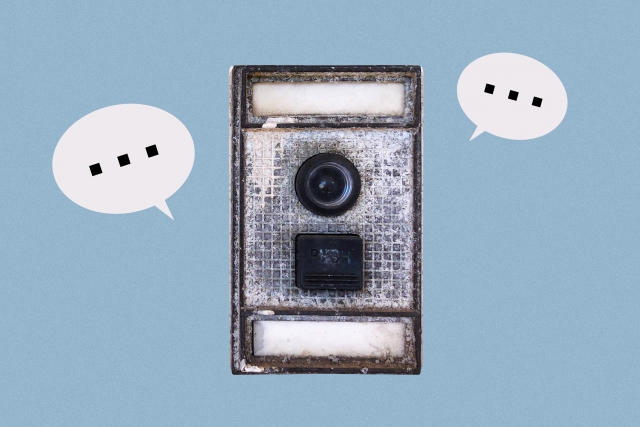
- インターホン押さないでステッカーは効果ある?
- インターホンが勝手に鳴ってしまう原因とは
- 消音機能付きインターホンの費用相場
- 古いインタホーンから交換するならおすすめの商品
- インターホンがならないようにする際よくある質問
インターホン押さないでステッカーは効果ある?


「インターホンを押さないでください」と書かれたステッカーは、一定の効果があるものの、相手や状況によって効力に差が出るのが実情です。目的は、不要な来訪や子どもの昼寝中など、静かに過ごしたい時間帯の呼び出しを防ぐことです。
宅配業者や営業スタッフには効果的
特に宅配業者や営業スタッフなど、業務として訪問している相手に対しては、このような表示を見れば配慮してくれる可能性が高いです。実際に、「昼寝中の赤ちゃんがいます」「在宅ワーク中のため静かにお願いします」など、具体的な理由を添えることで、より強い抑止効果が見込めます。
セールス訪問者には無視されるケースも…
一方で、全ての訪問者がステッカーに従うとは限りません。相手が急いでいたり、貼られていることに気づかなかった場合、チャイムを押されてしまうケースもあります。特にセールスや勧誘目的の訪問者には、ステッカーが無視されることも少なくありません。
集合住宅で共用エントランスがある場合
さらに、マンションや集合住宅のように「共用エントランス」がある場合、部屋の玄関前だけに貼っても、エントランスの呼び出しでは対応が間に合わないことがあります。こうした構造上の制約も考慮しなければなりません。
これらのことから、ステッカーはあくまで補助的な手段と考えるべきです。確実に音を止めたい場合は、音量調整・消音設定・物理的な遮音対策など、複数の方法を組み合わせるのが効果的です。
最後に、ステッカーは目立ちやすく、かつ丁寧な言葉づかいを選ぶこともポイントです。



強い言い方を避けつつ、意図がはっきり伝わる文言を選ぶと、相手に不快感を与えずに済みます。
インターホンが勝手に鳴ってしまう原因とは
誰も押していないのにインターホンが鳴るという現象は、意外と多くの家庭で発生しています。このような誤作動には、いくつかの典型的な原因がありますが、放置しておくと夜間の騒音や不安感につながるため、早めに原因を特定して対処することが重要です。
1.呼び出しボタンの物理的な不具合
まず考えられるのは、「呼び出しボタンの物理的な不具合」です。屋外の子機にあるボタンが長年の使用で押し込まれたままになっていたり、戻りが悪くなっていたりすると、微細な振動や風でも反応してしまうことがあります。台風後や寒暖差の激しい季節に突然起きやすい点も特徴です。
2.内部への水や虫の侵入
次に多いのが、「内部への水や虫の侵入」です。インターホンの構造は基本的に防水ですが、経年劣化や微細なすき間から雨水、結露、砂埃、または小さな虫が入り込むことがあります。これが基盤に触れると、ショートを起こして勝手に鳴る原因になります。
3.配線の劣化や接触不良
また、「配線の劣化や接触不良」も見逃せません。とくに壁の中で結線がゆるんでいたり、サビていたりすると、意図せず通電状態が変化して、誤作動が生じます。インターホンが古い場合や10年以上使い続けている場合には、この点を疑ってみる価値があります。
4.電波干渉
さらに見落としがちなのが、「電波干渉」です。無線通信に対応したインターホンでは、近所のトラックの無線、アマチュア無線、電子レンジなどの影響で誤動作が起きることがあります。特にワイヤレス式の機器はこの影響を受けやすいため、通信周波数が近い家電が周囲にないかも確認しておきたいポイントです。
5.人為的な要因
そして最後に「人為的な要因」も、可能性として考えるべきです。ピンポンダッシュや悪意のあるいたずら、空き巣の下見といったケースでは、防犯上のリスクも高まります。来訪者を確認できるカメラ付きのインターホンや録画機能を備えた機種への交換も、有効な対策になるでしょう。
このように、インターホンが勝手に鳴る原因は多岐にわたります。



ひとつずつ確認し、改善が難しい場合には専門業者への点検依頼を検討することが望ましいです。
消音機能付きインターホンの費用相場


消音機能が付いたインターホンを導入する場合、選ぶ機種や設置条件によってかかる費用は大きく異なります。価格の目安を把握しておくことで、予算内で機能的な製品を選びやすくなります。
本体価格の相場
まず、本体価格は機能のシンプルさにより大きく変動します。通話と呼び出しのみの基本モデルであれば、5,000円〜10,000円程度で購入できます。音量調整や消音設定が可能な製品でも、一般家庭向けのものであれば10,000円台前半から手に入ることが多いです。
高機能インターホンや録画機能付きモデル
一方で、モニター付きの高機能インターホンや録画機能付きモデルでは、15,000円〜40,000円ほどの価格帯が主流となります。さらに、スマートフォン連携や防犯カメラの映像確認が可能な多機能モデルでは、50,000円以上の製品も存在します。機能が増えるほど価格も上がるため、目的に合った選択が大切です。
タイプ別の工事費用
次に考慮すべきは工事費用です。現在のインターホンと同じタイプに交換するだけであれば、配線工事なしで済む場合もあり、費用は5,000円〜10,000円前後で収まることがあります。ただし、電源直結式や壁内配線が必要なモデルでは、工事費が20,000円〜40,000円に達することもあります。
とくに賃貸住宅では、工事が制限されている場合もあるため、事前に管理会社へ確認することが重要です。
また、ワイヤレスタイプのインターホンであれば、配線工事が不要で自分でも取り付けが可能なため、設置コストを抑えることができます。最近ではワイヤレスでも消音設定ができる製品が増えており、賃貸でも導入しやすい選択肢になっています。
このように、消音機能付きインターホンの導入には「本体価格+設置費用」の両面を、考える必要があります。



予算に応じて、最低限の機能だけを求めるのか、防犯性や快適性も重視するのかを検討すると、無駄な出費を防げるでしょう。
古いインタホーンから交換するならおすすめの商品
古いインターホンを使い続けていて、「音がうるさい」「消音機能がない」「誤作動が多い」といった悩みを抱えている方には、現代の便利な機能を備えた機種に交換することをおすすめします。近年のインターホンは、消音や録画、ワイヤレス対応など多機能化が進んでおり、生活の質を大きく向上させてくれます。
| 製品名 | 主な特徴 | おすすめポイント |
|---|---|---|
| パナソニック VL-SGZ30 | ワイヤレス式、電池駆動、ミュート設定可 | 配線不要で簡単設置、防犯にも対応 |
| アイホン JS-12E | ズーム・角度調整カメラ、消音機能付き | 操作が直感的、顔がしっかり確認できる |
| パナソニック VL-SE30XL | 録画機能、LEDライト、増設モニター対応 | 夜間対応、防犯強化、戸建てに最適 |
「パナソニックVL-SGZ30」シリーズ
特におすすめしたいのは、「パナソニックVL-SGZ30」シリーズです。ワイヤレス仕様のため配線工事が不要で、設置が簡単なのが特長です。呼び出し音の音量調整やミュート設定が可能なほか、来訪者の映像も確認できるため、防犯対策としても有効です。玄関子機は電池駆動で、最大2年間使用できる省エネ設計も魅力です。
「アイホンJS-12E」シリーズ
また「アイホンJS-12E」シリーズも、人気があります。ズームや角度調整ができるカメラを搭載し、訪問者の顔をしっかり確認できる点が安心です。操作画面が直感的でわかりやすく、機械が苦手な方でも使いやすい仕様となっています。もちろん、チャイムの音量設定や消音機能も搭載されています。
「パナソニックVL-SE30XL」
もう一つ注目したいのが、「パナソニックVL-SE30XL」です。録画機能が備わっており、留守中の訪問者を後から確認できます。LEDライト付きで夜間でも来訪者の顔がカラーで見える点は、防犯面でも非常に安心です。室内モニターを増設すれば、2階でも来客に気づけるようになるため、戸建て住宅にも適しています。
これらの製品は、どれも音量の調整や消音機能が標準搭載されており、古いインターホンでは難しかった細かい設定が可能です。さらに、操作性やデザイン性にも優れており、インテリアにも馴染みやすくなっています。
ただし、設置には機種ごとに条件が異なるため、自宅の電源方式(電池式・コード式・直結式)や壁面のスペースを事前に確認しておくことが重要です。必要であれば、販売店やメーカーに相談し、最適な機種を選びましょう。
交換することで、ただ音を消すだけでなく、快適さと安心感を得られる製品が多数あります。



生活スタイルに合ったインターホンを選ぶことが、毎日のストレス軽減にもつながります。
インターホンがならないようにする際よくある質問
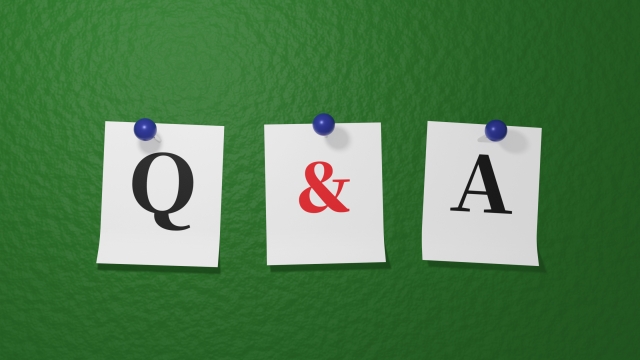
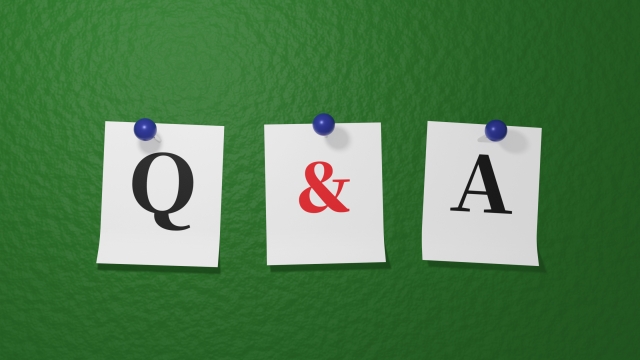
インターホンの音を消したいと考える方は多いですが、いざ対応しようとすると「本当に音を消して大丈夫?」「法律や賃貸契約に違反しない?」など、さまざまな疑問が浮かびがちです。ここでは、よく寄せられる質問とその回答をわかりやすく紹介します。
- インターホンの音を消すと宅配便の受け取りに支障は出ませんか?
-
はい、影響が出ることがあります。音を完全に消してしまうと、来客や宅配に気づけず、再配達になるケースもあります。対策としては、音は消しても光で知らせる「光チャイム」や、別の部屋で通知が受け取れる機器を併用するのが有効です。
- 電源を切ったり、線を抜いたりしても問題ないですか?
-
構造によっては問題ありませんが、電源直結式のインターホンでは無資格での配線作業は法律違反となる恐れがあります。また、集合住宅では共用設備に該当することもあるため、事前に管理会社や大家への確認が必要です。
- 音が鳴らないようにしても、呼び出しランプは光りますか?
-
これは機種によります。音量を「切」に設定しても、光やモニター画面で来客が分かるようになっているタイプもあります。事前に取扱説明書を確認し、通知方法がどうなるか把握しておくと安心です。
- ステッカーで「押さないで」と伝えるだけでも効果ありますか?
-
一部の来客、特に宅配業者には有効ですが、完全な抑止力ではありません。強制力がないため、すべての訪問者が従うわけではない点には注意が必要です。補助的な対策と考え、音量設定や物理的な遮音と組み合わせるとよいでしょう。
- 設定しても音が鳴り続ける場合は故障ですか?
-
可能性はあります。音量を「消音」に設定しているのに鳴る場合、内部の不具合や基盤の劣化が考えられます。長期間使用している機種であれば交換を検討するか、業者に点検を依頼しましょう。
このように、インターホンを鳴らないようにするには、単純に音を消すだけでなく、生活への影響や設備の仕様を理解することが大切です。



安全・快適に過ごすためにも、正しい方法で対応しましょう。
インターホンがならないようにするためのポイント総括
記事のポイントを、まとめます。
- 音量設定を「小」または「切」に変更できる、機種を活用する
- 音量つまみや消音スイッチが、本体側にある場合もある
- 消音設定は、来客に気づけないというデメリットもある
- ミュート中でも光や別室のチャイムで、通知できる方法がある
- 耐震ジェルマットを使えば、スピーカーの音を軽減できる
- 電源コード式は、コンセントを抜けば音を止められる
- 電池式の場合は、電池を外せば機能を停止できる
- 電源直結式は、ブレーカーを使うか業者に依頼すべき
- 受話器型インターホンでは、外しておくと音が鳴らない場合がある
- 音量設定が画面に表示されない機種では、状態確認が難しい
- 電源再起動で、音量設定が初期化される機種もある
- 高齢者のいる家庭では、音が小さすぎると気づかれにくい
- スピーカー位置が不明な機種は、全体を布で覆う対策が有効
- ワイヤレスチャイムなどに交換すれば、光通知のみに切り替え可能
- ステッカーの効果は限定的で、セールス訪問者には無視されがち
【参考】
>>ポスト一体型のインターホン交換方法って?基礎知識や費用と注意点
>>インターホンとドアホンの違いとは?用途や特徴と失敗しない選び方
>>スマホ連動の後付けインタホーンをマンションに最適な設置と活用法
>>インターホンが別の部屋で聞こえない?原因と最適な解決策を徹底解説
>>古いタイプのインターホンは簡単に交換できる?費用や方法を徹底解説
>>インターホンを何回も鳴らす理由って?警察への通報や対処法を解説
>>インターホンのブレーカーが落ちる原因は?対処法と交換時の注意点
>>インターホンが両面テープで落ちるのはなぜ?原因と対策を徹底解説
>>インターホンで履歴が残らない時の対処法って?7つの原因と解決策