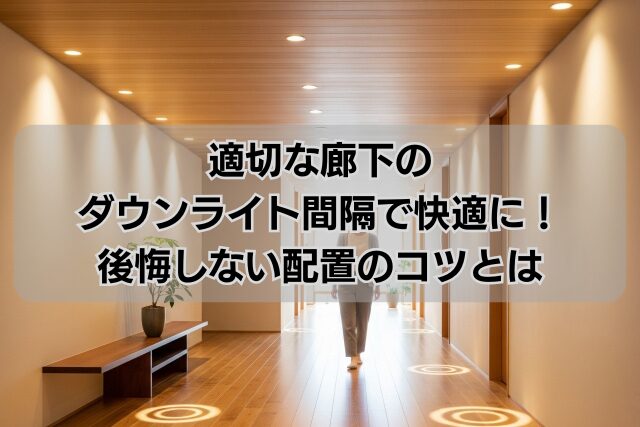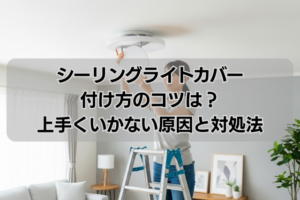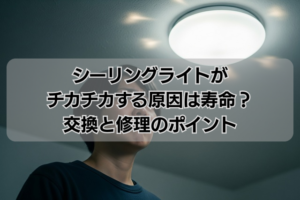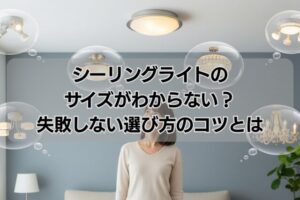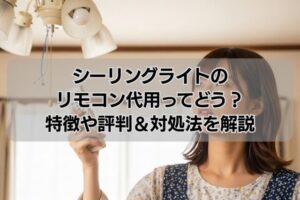家づくりにおいて、意外と見落とされがちなのが廊下の照明計画です。特に「廊下のダウンライトの適切な間隔とは?」「明るさはどのくらいが目安なのだろう?」といった疑問は、多くの方が抱える悩みではないでしょうか。
この記事では、ダウンライトの標準的なワット数から、設置で後悔しないための注意点まで、専門的な視点から詳しく解説します。
さらに、空間をおしゃれに見せる壁寄せのポイント、集光と拡散タイプのどちらが良いかといった選択基準、そして万が一、設置後に暗いと感じた時の具体的な対処法にも触れていきます。
廊下におすすめのダウンライトやシーリングライトの選び方から、修理や交換に困った際に頼りになる電気工事でおすすめ業者まで、あなたの疑問を全て解消する情報を網羅しました。
 ジロー
ジローこの記事を最後まで読めば、あなたの家の廊下を快適で美しい空間に変えるための、最適な照明計画がきっと見つかるはずです。
【記事のポイント】
1.廊下のダウンライトを設置する際の、適切な間隔
2.明るさやワット数など、照明計画の基本
3.おしゃれな空間を演出する、応用テクニック
4.設置後のトラブル対処法や、業者選びのポイント
失敗しない廊下のダウンライト間隔の基本


- 廊下のダウンライトの適切な間隔とは?
- 廊下のダウンライトの明るさはどのくらいが目安?
- 廊下のダウンライトの標準的なワット数
- 廊下のダウンライトで後悔しないための注意点
- 廊下におすすめのダウンライトやシーリングライト
廊下のダウンライトの適切な間隔とは?


廊下にダウンライトを設置する際、その間隔は2.7m〜4.5m程度を目安に考えるのが一般的です。多くの方は「廊下は明るい方が安全…」と考えがちですが、実は少し暗めに設定する方が、家全体の空間としてバランスが取れます。
その理由は、廊下が必要以上に明るいと、隣接するリビングなどの部屋が相対的に暗く感じてしまうからです。また、夜中にトイレなどで廊下に出た際、照明が明るすぎると目が冴えてしまい、リラックスを妨げる一因にもなりかねません。
大切なのは、空間全体を均一に明るくすることではなく、必要な明るさを必要な場所にだけ届けるという考え方です。
実際の検証データによると、4.5mの廊下に2灯(4.5m間隔)設置した場合でも、思った以上に明るさが確保でき、落ち着いた空間になると報告されています。一方で、2.7m間隔で設置すると、しっかりとした明るさが得られます。これ以上短い1.8mといった間隔で設置すると、多くの場合で明るすぎると感じるため、避けた方が賢明でしょう。



以上の点を踏まえると、コスト削減や空間のすっきり感を考慮するならば4.5m間隔、明るさを重視する方でも2.7m間隔を上限として計画するのが、失敗しないための鍵となります。
廊下のダウンライトの明るさはどのくらいが目安?


廊下の照明を計画する上で、明るさの具体的な目安は、照度を示すルクス(lx)という単位で「50lx程度」とされています。これは、JIS(日本産業規格)が推奨する住宅の廊下の照度基準でもあります。
| 場所 | 推奨照度 |
|---|---|
| 廊下・階段 | 50 lx |
| 居間(団らん時) | 100 lx |
| 居間(読書時) | 500 lx |
| 食堂(食事時) | 200 lx |
| 厨房(調理台) | 200 lx |
| 書斎・勉強室 | 500 lx |
なぜなら、前述の通り、廊下はあくまで部屋と部屋をつなぐ「通路」であり、リビングや書斎のように長時間を過ごしたり、細かい作業をしたりする場所ではないからです。
主要な部屋よりも廊下が明るいと、部屋に入ったときに暗く感じてしまい、空間の印象を損なう可能性があります。家全体の照明計画は、各空間の役割に応じた明るさのバランスを取ることが求められます。
明るさを表すもう一つの単位にルーメン(lm)がありますが、これは光源そのものが発する光の総量を指します。一般的にLED照明では「1畳あたり300〜500lm」が目安とされますが、これは部屋全体を照らすシーリングライトを基準とした考え方です。
ダウンライトのように局所的に照らす照明では、設置する位置や数によって明るさの感じ方が大きく変わるため、一概には言えません。



これらのことから、単純に照明器具のルーメン値だけで判断するのではなく、空間全体の調和を考え、50lxという照度を目安に、眩しすぎず、かつ安全に歩行できる程度の落ち着いた明るさを目指すことが大切です。
廊下のダウンライトの標準的なワット数


廊下のダウンライトを選ぶ際、一般的には60W相当のLED電球が標準とされてきました。しかし、近年のLED照明は性能が向上しており、多くの場合40W相当でも十分に明るさを確保できます。
ここで注意したいのは、「W(ワット)」「W相当」の違いです。
ワットは消費電力を示す単位であり、LED以前の白熱電球時代は、このワット数が明るさの目安として使われていました。しかし、LEDは非常に少ない消費電力で明るく光るため、60W相当と表記されていても、実際の消費電力は8W前後です。
現在の明るさの正式な指標は「lm(ルーメン)」であり、60W相当のLED電球は一般的に約810lmの光量を持ちます。
例えば、長さ3.5mの廊下を照らす場合、60W相当のダウンライトが2つあれば十分な明るさが得られることが多いです。ただし、これは照明器具の光の広がり方(配光)によっても変わってきます。
光が広範囲に広がる拡散タイプの器具を選べば、少ない数でも効率よく廊下を照らすことが可能です。



そのため、ワット数だけで照明を選ぶのではなく、必ずルーメン値(lm)を確認し、どのような光の広がり方をする器具なのかを考慮して選定することが、エネルギーの無駄をなくし、適切な明るさを得るためのポイントとなります。
廊下のダウンライトで後悔しないための注意点


廊下のダウンライト計画で後悔しないためには、間隔や明るさ以外にもいくつかの重要な注意点があります。これらを事前に把握しておくことで、より快適で使いやすい廊下空間を実現できます。
配置は「行き先の壁」を照らす
ダウンライトを廊下の中央に均等に配置するだけでなく、「行き先の壁」を照らすように設置するのが効果的です。人間は、進む先が明るいと心理的な安心感を覚え、空間の奥行きも感じやすくなります。
これは「サバンナ効果」とも呼ばれ、視覚的に廊下が短く感じられるメリットもあります。同じ灯数でも、配置を工夫するだけで空間の印象は大きく変わります。
収納の前に照明を配置する
廊下に収納スペースがある場合は、その扉の真ん前にダウンライトを配置することを意識してください。照明の位置が少しずれるだけで、扉の影になってしまい、収納の中が暗くて見えにくくなるという失敗がよくあります。
「動線+収納+照明」をワンセットで考えるのが、プロの設計テクニックです。
センサーの使い分けを検討する
夜間の使用を考えると、センサースイッチは非常に便利です。しかし、ダウンライトがセンサーで点灯すると、夜中に目が慣れていない状態では非常に眩しく感じることがあります。
この対策として、ダウンライト本体は壁のスイッチで操作するようにし、夜間の歩行用には人感センサー付きの「足元灯」を別途設置する組み合わせがおすすめです。これにより、必要な時だけ足元を優しく照らし、快適性と安全性を両立できます。
調光・調色機能を活用する
可能であれば、明るさを調整できる「調光機能」や、光の色味(白っぽい光からオレンジ色の光まで)を変えられる「調色機能」が付いたダウンライトを選ぶと、活用の幅が大きく広がります。



時間帯や気分に合わせて雰囲気を変えることができ、より質の高い空間づくりに貢献します。
廊下におすすめのダウンライトやシーリングライト


廊下の照明選びでは、空間の特性や求める雰囲気に合わせて器具を選ぶことが大切です。ここでは、廊下に適したダウンライトやその他の照明器具について、それぞれの特徴と共にご紹介します。
ダウンライト
ダウンライトは天井に埋め込むため、空間がすっきりと見えるのが最大のメリットです。ほこりが溜まりにくく、掃除が楽な点も廊下に向いています。
1.拡散タイプ
光を広範囲にふんわりと広げ、廊下全体を均一に明るくしたい場合に適しています。通路としての機能性を重視するなら、このタイプが基本となります。
2.ユニバーサルタイプ
光の向きを自由に変えられるため、壁に飾った絵や写真、アクセントウォールなどを照らして、ギャラリーのような空間を演出したい場合におすすめです。
3.浅型タイプ
天井裏のスペースが限られている場合でも、設置しやすいように設計された薄型のダウンライトです。リフォームなどで検討する際に選択肢となります。
シーリングライト
シーリングライトは、天井に直接取り付けるタイプの照明です。一つの器具で広範囲を照らせるため、ダウンライトよりも少ない数で廊下全体の明るさを確保できるのが特徴です。
特に天井高が低い廊下の場合、ダウンライトよりも光源が目に入りにくく、圧迫感を軽減できるメリットがあります。近年では、天井に馴染む超薄型のデザインも増えています。
足元灯(フットライト)
夜間の、安全な歩行をサポートするのが足元灯です。ダウンライトのように天井照明を点灯させることなく、足元だけを優しく照らしてくれます。
1.明るさセンサー付き
周囲が暗くなると常時点灯するタイプです。窓がなく日中も暗い廊下では点きっぱなしになる点に注意が必要です。
2.明るさ+人感センサー付き
暗いときに人が近づいた時だけ点灯するタイプです。無駄な点灯を防ぎ、省エネ効果が高いのが魅力です。



ご自身の環境に沿った空間イメージで、照明器具をチョイスしてください。
廊下のダウンライト間隔で知るべき応用知識


- 廊下のダウンライトをおしゃれに壁寄せするポイント
- 廊下のダウンライトは集光と拡散ならどちらが良い?
- 廊下のダウンライトが暗いと感じた時の対処法
- 修理や交換に困ったら電気工事でおすすめ業者
- 廊下のダウンライトの間隔でよくある質問
廊下のダウンライトをおしゃれに壁寄せするポイント


廊下のダウンライトを単なる照明としてではなく、空間を演出するアイテムとして活用したい場合、「壁寄せ」という配置テクニックが非常に効果的です。これは、ダウンライトを廊下の中央ではなく、意図的にどちらかの壁際に寄せて設置する方法です。
壁寄せにすることで、光が壁面をなめるように当たり、壁の素材感や陰影が際立ちます。これにより、空間にメリハリと奥行きが生まれ、通路だった廊下が表情豊かな空間へと変化します。
特に、アクセントクロスや珪藻土、タイルなど、こだわりの素材を使っている壁面を照らすと、その魅力が一層引き立ちます。
このテクニックを成功させるポイントは、使用するダウンライトの種類です。壁面を美しく見せるためには、光がある程度絞られた「集光タイプ」や、光の角度を調整できる「ユニバーサルダウンライト」を選ぶのが良いでしょう。光が広がりすぎる拡散タイプでは、壁を照らす効果が薄れてしまいます。
壁からの距離は30cm〜50cm程度が一般的ですが、これは天井高や使用する器具によっても変わります。



照明計画の段階で、どのような光の広がりになるかをシミュレーションしながら位置を決定することが、理想の空間を実現する鍵となります。
廊下のダウンライトは集光と拡散ならどちらが良い?


ダウンライトを選ぶ際に必ず直面するのが、「集光タイプ」「拡散タイプ」のどちらを選ぶかという問題です。この選択は、廊下に求める機能や雰囲気によって決まります。両者の特性を理解し、目的に合わせて使い分けることが肝心です。
| タイプ | メリット | デメリット | おすすめの人 |
|---|---|---|---|
| 集光タイプ | ・メリハリのある空間 ・アートを強調できる ・スタイリッシュな印象 | ・全体が暗く感じることも ・影ができやすい | ・ギャラリー風にしたい人 ・空間デザインにこだわる人 |
| 拡散タイプ | ・均一に明るい ・柔らかく安心感のある光 ・実用性が高い | ・平坦で無個性に見えることも ・演出効果は弱め | ・安全性を重視する人 ・シンプルな空間が好きな人 |
集光タイプの特徴
集光タイプは、光を一点に集めるようにピンポイントで照らすのが特徴です。
壁に飾ったアートやグリーン、壁面の素材感などをドラマチックに照らし、空間にメリハリを生み出します。視線を集めたい場所を強調できるため、スタイリッシュでホテルライクな演出が可能です。
照らしている範囲以外は暗くなるため、廊下全体の均一な明るさを確保するには不向きです。実用性よりもデザイン性を重視する場合の選択肢と言えます。
拡散タイプの特徴
拡散タイプは、光を広範囲に柔らかく広げ、空間全体をふんわりと照らします。
廊下全体を均一な明るさで照らすことができるため、通路としての安全性や視認性が高まります。落ち着いた、安心感のある空間づくりに適しています。
全体が均一に明るくなる分、メリハリがなく、やや平坦でのっぺりとした印象になりがちです。



廊下を通路として、安全かつ快適に使いたい場合は「拡散タイプ」を、インテリアの一部としておしゃれに演出したい場合は「集光タイプ」を壁際に配置するなど、目的を明確にして選ぶことが失敗しないための道筋です。
廊下のダウンライトが暗いと感じた時の対処法


万が一、新築やリフォーム後に「廊下のダウンライトが思ったより暗い…」と感じてしまった場合でも、諦める必要はありません。いくつかの対処法を検討することで、明るさを改善することが可能です。
対処法1:照明器具を追加する
最も手軽で効果的なのは、既存の照明に加えて新たな照明器具を導入することです。
1.スタンドライト(フロアスタンド)
床に置くタイプの照明で、コンセントがあればどこでも設置できます。デザインも豊富で、インテリアのアクセントにもなります。間接照明として壁や天井を照らすと、空間に広がりと明るさが生まれます。
2.テーブルライト
廊下に棚やコンソールテーブルがある場合に有効です。手元を明るく照らし、空間に温かみを加えます。
対処法2:壁や天井のクロスを明るくする
部屋の明るさは、照明だけでなく壁や天井の色にも大きく影響されます。現在のクロスが暗めの色であれば、白やアイボリーといった明るいトーンのものに貼り替えることで、光の反射率が高まり、空間全体が明るい印象に変わります。
全面の貼り替えが難しければ、一面だけをアクセントとして変えるだけでも効果が期待できます。
対処法3:ダウンライト本体の増設や交換を行う
根本的な解決を目指すなら、電気工事を伴うダウンライトの増設や交換が選択肢となります。これは専門的な作業が必要ですが、最も確実な方法です。
1.器具の交換
現在設置されているダウンライトを、より明るい(ルーメン値の高い)製品に交換します。
2.器具の増設
新たにダウンライトを追加で設置します。どこに、どのくらいの間隔で増やすかは、専門の業者と相談しながら慎重に決める必要があります。



これらの方法を検討し、ご自身の状況や予算に合った最適な解決策を見つけてください。
修理や交換に困ったら電気工事でおすすめ業者


ダウンライトの増設や交換、故障時の修理は、電気工事士の資格が必要な専門作業です。安全かつ確実に行うためには、信頼できるプロの業者に依頼することが不可欠です。ここでは、全国対応で実績のあるおすすめの電気工事業者をご紹介します。
電気工事110番
「電気工事110番」は、日本全国どこでも24時間365日対応してくれる大手の電気工事業者です。最短で即日対応も可能で、突然のトラブルにも迅速に駆けつけてくれるのが強みです。
見積もりは無料で、作業前に料金を明確に提示してくれるため、安心して依頼できます。ダウンライトの増設からスイッチの交換まで、幅広い電気工事に対応しています。
こちらの記事「電気工事110番の口コミの真相って?実際の評判や特徴を完全ガイド」では、口コミやメリットデメリットなど他、評判や特徴を徹底解説しましたので、是非参考にしてください♪
テイクサービス
「テイクサービス」も全国をカバーする電気工事業者で、顧客満足度の高さを謳っています。特に、丁寧なヒアリングと現地調査に基づいて、最適なプランを提案してくれると評判です。
料金体系も分かりやすく、Webサイトで概算費用を確認できる点も安心材料の一つです。照明に関する悩みや要望をじっくり相談したい方におすすめです。
電気の工事屋さん
「電気の工事屋さん」は、地域に密着したサービスを展開しつつ、全国のネットワークを持つ業者です。こちらも24時間受付対応で、緊急の依頼にも応えてくれます。
照明器具の選定から相談に乗ってくれるなど、利用者に寄り添ったサービスが特徴です。施工後の保証がしっかりしている点も、信頼できるポイントと言えます。
これらの業者は、いずれも無料で見積もりを依頼できます。



複数の業者から見積もりを取り、料金やサービス内容を比較検討した上で、ご自身に最も合った業者を選ぶと良いでしょう。
廊下のダウンライトの間隔でよくある質問


ここでは、廊下のダウンライトの間隔や計画に関して、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- 長さ3.5mの廊下の場合、ダウンライトは何個必要ですか?
-
求める明るさや使用するダウンライトの性能(配光)によって異なりますが、一般的には2灯でも十分な場合が多いと考えられます。2.7m間隔を一つの基準とすると、両端から少し内側に入った位置に2灯設置する計画が考えられます。
もし、しっかりとした明るさが欲しい、あるいは廊下に収納などがあり作業性を高めたい場合は、3灯設置することも選択肢になります。最終的には、空間全体のバランスを見て決めるのが良いでしょう。
- ダウンライトと足元灯、どちらがおすすめですか?
-
主照明と補助照明として、役割が異なりますので、併用するのが最もおすすめです。日中や来客時など、廊下全体を明るくしたい時はダウンライトを使用します。
一方、夜中に家族が寝静まった後でトイレに行く際などは、眩しすぎず安全に歩行できる足元灯が活躍します。ダウンライトだけで済ませるよりも、格段に快適性が向上します。
- センサーはダウンライトにつけた方が良いですか?
-
センサーは非常に便利ですが、注意が必要です。前述の通り、夜間にダウンライトがセンサーで突然点灯すると、非常に眩しく感じることがあります。
これを避けるため、ダウンライトは壁スイッチでの手動操作とし、夜間用の足元灯に人感センサーを付けるという組み合わせが、現在では主流の考え方となっています。これにより、利便性と快適性を両立させることができます。



よくあるQ&Aも、参考にしてください。
【総括】廊下のダウンライト間隔で快適を実現するコツ
この記事で解説してきた、快適な廊下照明を実現するためのポイントをまとめました。理想の空間づくりのために、ぜひこれらのコツを参考にしてください。
- 廊下照明は、明るすぎない「暗め」が基本
- ダウンライトの間隔は、2.7m〜4.5mを目安に
- 明るすぎる、1.8m間隔は避ける
- 他の部屋との、明るさのバランスを考慮する
- 廊下の推奨照度は、50ルクス程度
- ワット数より、ルーメン値と配光を確認
- 行き先の壁を照らすと、安心感と奥行きが出る
- 収納の扉の前に配置すると、中が見やすい
- 壁寄せにすると、空間がおしゃれになる
- 集光タイプは演出、拡散タイプは均一な明るさ向き
- 夜間の眩しさを防ぐには、足元灯が有効
- ダウンライトのセンサーは、夜間眩しい可能性に注意
- 暗い場合は、増設や交換も選択肢
- 照明計画は、専門業者への相談も検討
- 最終的なダウンライト廊下間隔は、生活動線を考えて決める
【参考】
>>ダウンライト一体型と交換型の見分け方のコツ!特徴やポイントを解説
>>ダウンライトが眩しい悩みはカバーで解決?効果や選び方のポイント
>>ダウンライトに人感センサーの後付けは可能?費用や注意点を徹底解説
>>【完全ガイド】シャンデリアの外し方を徹底解説!費用や注意点とは
>>シーリングライトのリモコン代用ってどう?特徴や評判&対処法を解説
>>ダウンライトをやめたい方へ…交換方法と費用や後悔しない注意点とは
>>シーリングライトのサイズがわからない?失敗しない選び方のコツとは
>>シーリングライトのアダプターが外れないを解決!原因と対処法を解説
>>シーリングライトがチカチカする原因は寿命?交換と修理のポイント
>>シーリングライトカバー付け方のコツは?上手くいかない原因と対処法