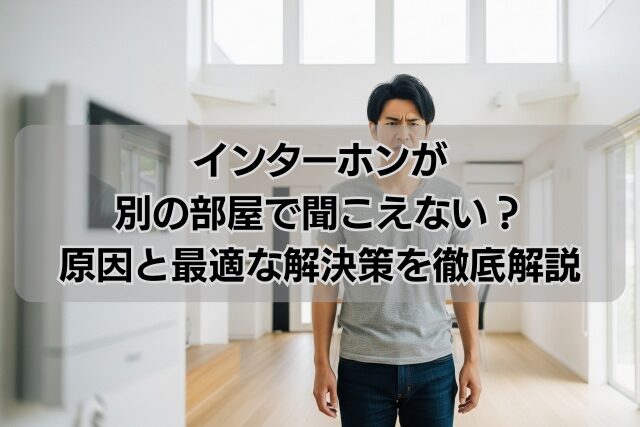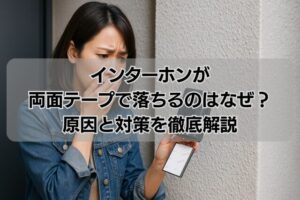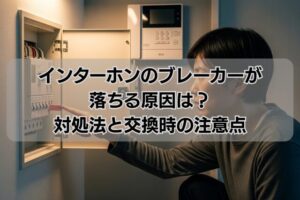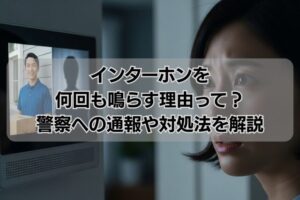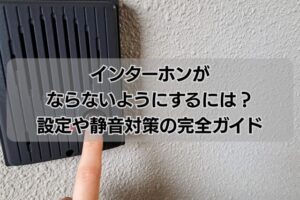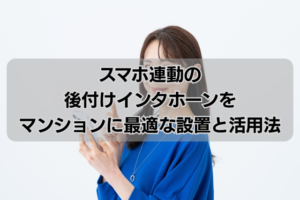「二階の書斎で仕事に集中していると、階下のインターホンに全く気づかない…」「キッチンで換気扇を回していたら、宅配便を逃してしまった…」など、家のどこにいるかによってインターホンの音が聞こえず、困った経験はありませんか?
実は、この悩みはあなただけのものではありません。現代の住宅事情やライフスタイルの変化により、多くの方が家の中の聞こえない死角に、ストレスを感じています。
この記事では、インタホーンが別の部屋で聞こえない理由を解明し、インタホーンが聞こえるようにする解決策を具体的にご紹介します。
また、二階にインタホーンを設置するメリットデメリットから、賃貸でインタホーンが聞こえない場合の対処法、さらにはインタホーンが聞こえない高齢者への対策まで、あらゆる状況を想定した情報をお届けします。
二階にインタホーンを後付けする方法や、光るインタホーンを後付けする費用はどのくらいか、そして聞こえない場合にスマホ応対できるのかといった、より具体的な疑問にもお答えします。
 ジロー
ジロー今人気の、交換するならおすすめのインターホン情報も交えながら、あなたの住まいと暮らしに最適な解決策を見つける、お手伝いをします。
【記事のポイント】
1.インターホンが、別室で聞こえない主な原因
2.状況別の、具体的な解決策と選び方
3.後付けや交換にかかる、費用の目安
4.賃貸や高齢者世帯での、注意点と対策
インターホンが別の部屋で聞こえない原因と対策


ここでは、インターホンが別の部屋や階で聞こえにくくなる根本的な原因と、それぞれの状況に応じた基本的な対策について掘り下げていきます。ご自身の住環境と照らし合わせながら、最適な解決策のヒントを見つけてください。
- インタホーンが別の部屋で聞こえない理由
- インタホーンが聞こえるようにする解決策
- 二階にインタホーンを設置するメリットデメリット
- 賃貸でインタホーンが聞こえない場合の対処法
- インタホーンが聞こえない高齢者への対策
インタホーンが別の部屋で聞こえない理由


インターホンの呼び出し音が特定の部屋で聞こえないという問題は、決して珍しいことではありません。その背景には、建物の構造から日常生活の過ごし方まで、複数の要因が複雑に絡み合っています。
音の物理的な特性
まず最も基本的な理由として、「音の物理的な特性」が挙げられます。音は空気の振動によって伝わるため、音源であるインターホンの親機から距離が離れるほど、音量は自然と小さくなります。特に1階のリビングから2階の寝室といったように階をまたぐ場合、その減衰は顕著です。
建物の構造
次に「建物の構造」が、大きく影響します。壁や床、ドアは音を遮る障害物となります。木造住宅であっても壁や床材によって音は吸収・反射され、相手側には届きにくくなります。
これが鉄筋コンクリート造のマンションなどになると、遮音性はさらに高まり、音が他の部屋へ伝わるのは一層困難になります。浴室のように、防水性やプライバシー確保のために特に音を遮る設計になっている場所では、呼び出し音はほとんど聞こえないと考えた方がよいでしょう。
家の中の生活音
また、意外と見落としがちなのが、家の中の「生活音」です。テレビの音、掃除機や洗濯機の稼働音、キッチンでの換気扇や調理器具の音など、私たちの周りは常に様々な音で満たされています。これらの生活音が、インターホンの呼び出し音をかき消してしまうことも少なくありません。
高気密・高断熱化
さらに、近年の住宅は省エネ性能を高めるために、「高気密・高断熱化」が進んでいます。これは外の騒音をシャットアウトし、室内の温度を快適に保つ上で非常に有効ですが、副作用として家の中の音も伝わりにくくする一因となっているのです。
インターホン自体の設定
最後に「インターホン自体の設定」も、関係しています。多くのインターホンは、親機が設置されているすぐ近くで聞くことを前提に設計されており、家全体に響き渡るほどの大音量が出るようには作られていない場合がほとんどです。



これらの要因が一つ、あるいは複数重なることで、「別の部屋で聞こえない」という問題が発生すると考えられます。
インタホーンが聞こえるようにする解決策


インターホンの音が聞こえない問題を解決するには、いくつかの有効な方法が存在します。工事の要否や機能性、費用などを比較検討し、ご自身のライフスタイルや住環境に最も合ったものを選ぶことが大切です。
ワイヤレスチャイムの増設
最も手軽で効果的な解決策の一つが、「ワイヤレスチャイム」の増設です。これは既存のインターホンとは別に、もう一つチャイムを設置する方法です。
送信機(押しボタン)を玄関子機の隣に設置し、受信機を音が聞こえにくい部屋に置くだけで、配線工事は一切不要です。訪問者に両方のボタンを押してもらう必要はありますが、非常に安価で簡単に導入できる点が大きなメリットと言えます。
サウンドモニターや音感センサー付きチャイム
次に考えられるのが、「サウンドモニター」「音感センサー付きチャイム」の活用です。これは、インターホンの親機が鳴るピンポーンという音自体をセンサーで感知し、離れた場所にある受信機(スピーカー)を鳴らす仕組みです。
吸盤で親機に取り付けるタイプなどがあり、これも工事不要で手軽に設置できます。受信機側で光やメロディの種類を選べる製品も多く、生活音の中でも気づきやすい工夫がされています。
ただし、インターホン以外の音にも反応してしまう可能性がある点には注意が必要です。
モニター子機の増設
より根本的な解決を目指すなら、「モニター子機」の増設がおすすめです。お使いのインターホンが対応機種である必要はありますが、ワイヤレスで持ち運び可能な子機を増やすことで、家のどこにいても来客の映像を確認し、そのまま応答・通話ができます。1階まで降りていく手間が省けるため、利便性は格段に向上します。
これらの解決策は、それぞれに利点と注意点があります。例えば、ワイヤレスチャイムやサウンドモニターは安価で導入しやすい反面、通話機能はありません。一方でモニター子機は非常に便利ですが、対応機種の確認や他の方法に比べて費用がかかる場合があります。



どの方法が最適か、ご自宅の状況や何を最も重視するかを考えて選ぶのがよいでしょう。
二階にインタホーンを設置するメリットデメリット


一階にしかインターホンがないご家庭で、二階への増設を検討する方は少なくありません。二階にもインターホンがあれば生活が便利になることは想像できますが、具体的にどのようなメリットがあり、また一方でどのようなデメリットや注意点があるのかを把握しておくことが大切です。
メリット
1.来客対応の利便性向上
最大のメリットは、やはり「来客対応の利便性向上」です。二階で家事や仕事をしている際に来客があっても、わざわざ一階まで降りる必要がありません。
特にモニター付きのインターホンであれば、その場で相手の顔を確認できるため、不要なセールスなどであれば応対しないという判断も可能です。宅配便の受け取りもスムーズになり、再配達を依頼する手間を大幅に削減できます。
2.防犯性の向上
次に、「防犯性の向上」も大きな利点です。空き巣犯は、留守宅かを確認するためにインターホンを鳴らすことがあります。一階にしかインターホンがなく、二階にいて応答できなかった場合、留守だと思われて侵入されるリスクが高まります。二階ですぐに応答できれば、在宅していることを示せるため、犯罪の抑止力として機能します。
3.家族間のコミュニケーション
さらに、「家族間のコミュニケーション」にも役立ちます。例えば、お子様が帰宅した際にすぐに気づいて出迎えたり、鍵を忘れた家族を待たせることなく解錠したりできます。日々の小さなストレスが解消され、より安心で快適な住環境が実現するでしょう。
デメリットと注意点
1.設置費用…
一方、デメリットとしてまず考えられるのは「設置費用」です。インターホンの機種や工事内容によって費用は変動しますが、本体価格に加えて工事費が必要になる場合があります。特に壁内に配線を通す大掛かりな工事になると、費用は高額になる可能性があります。
2.増設不可能な場合も…
また、どのようなインターホンでも「増設できるわけではない」点にも、注意が必要です。現在お使いの親機に対応した子機や増設モニターでなければ設置できません。事前に自宅のインターホンのメーカーや型番を確認し、増設が可能かどうかを調べる必要があります。



これらのメリットとデメリットを総合的に判断し、ご自身のライフスタイルや予算に見合った選択をすることが、後悔のないインターホン増設につながります。
賃貸でインタホーンが聞こえない場合の対処法


賃貸物件にお住まいの場合、インターホンの問題は戸建て住宅とは異なる配慮が求められます。勝手に壁に穴を開けたり、大規模な配線工事を行ったりすることは基本的にできないため、解決策は「原状回復」を前提とした方法に限られます。
インターホン本体の確認
まず試すべきなのは、「インターホン本体の確認」です。音量設定が最小になっていないか、乾電池式のタイプであれば電池が消耗していないかをチェックしましょう。これらを確認しても改善しない場合、機器の経年劣化や故障の可能性が考えられます。
インターホンは物件の設備の一部ですので、不具合がある場合は自己判断で対処せず、まずは大家さんや管理会社に連絡して相談するのが基本です。
大家さんや管理会社に対応してもらえない場合や、故障ではなく構造上の問題で聞こえにくい場合には、工事不要で設置できる補助的な機器の導入が有効です。
ワイヤレスチャイムの設置
最も手軽なのは、「ワイヤレスチャイム」の設置です。送信機は両面テープで玄関ドアの横などに貼り付け、受信機は聞こえにくい部屋のコンセントに挿すか、電池式であれば好きな場所に置くだけです。退去時には簡単に取り外せます。
音感センサー付きチャイムを使用
もう一つの方法は、「音感センサー付きチャイム」です。これは既存のインターホン親機のスピーカー部分にセンサーを貼り付け、チャイム音を感知して別の受信機を鳴らす仕組みです。こちらも工事不要で、壁などを傷つける心配がありません。
これらの機器は、数千円程度から購入可能で、機械が苦手な方でも簡単に設置できるのが魅力です。ただし、これらの方法では来客があったことを知らせるのみで、通話はできません。通話機能まで求める場合は、より高機能な製品の検討が必要になります。



賃貸物件では、まず管理者に相談すること、そして許可なく建物を加工しないことを徹底し、規約の範囲内で最適な解決策を見つけることが重要です。
インタホーンが聞こえない高齢者への対策


ご高齢になると、加齢に伴う聴力の変化により、若い頃には問題なく聞こえていたインターホンの音も聞き取りにくくなることがあります。ご本人が「まだ大丈夫」と思っていても、実際には来客や大切な連絡に気づけていないケースも少なくありません。
離れて暮らすご家族にとっても、これは心配の種でしょう。
音以外の方法で知らせる
高齢者がインターホンを聞き取りにくい問題への対策として最も重要なのは、「音以外の方法」で来客を知らせる工夫をすることです。
効果的なのが、光で知らせる製品の導入です。これは「フラッシュチャイム」「光るチャイム」などと呼ばれ、インターホンの呼び出し音と連動して、非常に明るい光(フラッシュ)が点滅して来客を知らせます。
テレビを見ていたり、家事をしていて音が聞き取りにくい状況でも、視覚的に気づくことができます。既存のインターホンに後付けできる音センサータイプや、配線工事で連動させるタイプなどがあります。
バイブレーションで知らせる
さらに、「振動(バイブレーション)」で知らせる方法も有効です。胸ポケットやベルトに装着できる小型の携帯型受信機があり、呼び出しがあると本体が振動して知らせてくれます。庭仕事中や、補聴器を外している入浴後など、音や光にも気づきにくい状況でも確実に知らせを受け取れるため、安心感が高まります。
もちろん、インターホン自体の呼び出し音量を大きく設定したり、より大きな音が出る機種に交換したりすることも基本的な対策となります。製品によっては、音の高さを調整できるものもあり、ご本人が聞き取りやすい音域に設定することも可能です。
ご本人のプライドを傷つけないよう、「防犯のために、より安心できるようにしよう」といった形で、ご家族が変化に気づき、サポートを提案することがスムーズな導入の鍵となります。



音、光、振動といった複数の手段を組み合わせることで、聞こえの不安を解消し、安全で快適な毎日を支えることができます。
インターホンが別の部屋で聞こえない悩みの解消法


ここでは、二階への後付け工事の具体的な方法から、光やスマホを活用した最新の解決策、さらには製品選びのポイントまで、一歩踏み込んだ実践的な情報をご紹介します。あなたの悩みをスッキリ解消するための、最適な手段がきっと見つかります。
- 二階にインタホーンを後付けする方法
- 光るインタホーンを後付けする費用はどのくらい?
- インターホンが聞こえない場合にスマホ応対できる?
- 今人気の交換するならおすすめのインターホン
- インターホンが聞こえないに関するよくある質問
二階にインタホーンを後付けする方法


二階にインターホンを後付けする方法は、主に現在設置されているインターホンの電源方式によって、大きく異なります。方法を間違えると、ご自身でできる範囲を超えて専門的な資格が必要になるため、まずは自宅のインターホンがどのタイプかを確認することが不可欠です。
電源方式の確認
インターホンの電源方式は大きく分けて、「乾電池式」「電源コード式」「電源直結式」の3種類があります。
1.乾電池式・電源コード式(工事不要)
室内親機が乾電池で動いているタイプや、親機から出ているコードをコンセントに挿して使用しているタイプです。これらのインターホンに子機を増設する場合、多くはワイヤレスで接続するため、専門的な配線工事は必要ありません。
説明書に従って、親機と子機のペアリング設定を行うだけで、比較的簡単に設置できます。DIYでの取り付けも、十分可能です。
2.電源直結式(要電気工事士資格)
室内親機に電源コードが見当たらず、壁の中から直接電源を取っているタイプです。このタイプに有線の子機を増設したり、機種自体を交換したりする場合は、壁内の電気配線を扱う「内線工事」が必要となります。
この作業は「電気工事士」の国家資格を持つ専門家でなければ行うことが法律で禁じられています。無資格での工事は、非常にリスクが高いです。
後付けの具体的な流れ
資格が必要な「電源直結式」の場合、後付けはプロの業者に依頼するのが唯一の方法です。複数の業者から見積もりを取り、工事内容や費用を比較検討するとよいでしょう。
一方、ご自身で設置可能な「乾電池式」「電源コード式」のワイヤレス子機を増設する場合は、以下の流れで進めます。
1.対応機種の確認
現在の親機メーカーと型番を確認し、増設可能な子機のモデルを特定します。
2.子機の購入
特定した子機を、家電量販店やオンラインストアで購入します。
3.設置と設定
説明書をよく読み、子機を設置したい場所に固定します。その後、親機とのペアリング(接続設定)を行えば完了です。



安全かつ確実に取り付けるためにも、自宅の電源方式を正しく把握し、必要であれば迷わず専門業者に相談することが、賢明な選択と言えます。
光るインタホーンを後付けする費用はどのくらい?


インターホンの呼び出し音を光で知らせる「光るインターホン」は、耳が聞こえにくい方や、騒音の多い環境で過ごすことが多い方にとって非常に有効な解決策です。後付けする場合の費用は、選ぶ製品のタイプや機能によって大きく異なりますが、大まかな相場を把握しておくと製品選びの参考になります。
費用は、大きく分けて「製品本体の価格」と、場合によって発生する「工事費」の2つで構成されます。
製品本体の価格
光で知らせる製品には、いくつかのタイプがあり、それぞれ価格帯が異なります。
1.音感センサー付きワイヤレスタイプ
最も手軽で安価なのがこのタイプです。既存のインターホン親機のスピーカー部分に音を感知するセンサーを取り付け、チャイム音に反応して離れた場所の受信機が光と音で知らせます。工事不要で、製品価格は3,000円~8,000円程度が中心です。
2.ワイヤレスチャイムのフラッシュタイプ
前述のワイヤレスチャイムセットの中で、受信機が光る機能を持つものです。こちらも工事不要で、セットで4,000円~10,000円程度で購入できます。
3.システムとして連動させるタイプ
パナソニックの「光るチャイム」など、既存のインターホンシステムに有線で接続して、確実に連動させる専用機器もあります。この場合、製品本体の価格は15,000円~25,000円程度となり、機能性が高い分、価格も上がります。
工事費
工事不要のワイヤレスタイプを選べば、当然ながら工事費はかかりません。
一方で、システムとして連動させる有線タイプを設置する場合は、配線工事が必要になります。この工事は電気工事士の資格が求められる場合が多く、専門業者に依頼する必要があります。工事費の相場は、配線の状況や作業の難易度によって異なりますが、一般的には8,000円~30,000円程度を見ておくとよいでしょう。
要するに、手軽に試したい場合は工事不要のワイヤレスタイプが、総額10,000円以下で導入可能です。一方で、より確実な動作とシステム連携を求める場合は、製品代と工事費を合わせて数万円の費用がかかる可能性があるということです。



ご自身のニーズと予算に合わせて、最適な製品を選びましょう。
インターホンが聞こえない場合にスマホ応対できる?


インターホンの音が聞こえないという悩みに対し、スマートフォンの活用は非常に強力な解決策となります。近年普及が進んでいる「スマホ連動インターホン」を導入すれば、物理的にインターホンの呼び出し音が聞こえない場所にいても、手元のスマホで来客対応が可能になります。
スマホ連動インターホンの仕組みとメリット
スマホ連動インターホンは、インターネット回線を介して、インターホン親機とご自身のスマートフォンを連携させるシステムです。来客が玄関のチャイムを押すと、室内の親機が鳴ると同時に、専用アプリをインストールしたスマホに通知が届きます。
この仕組みによる最大のメリットは、場所に縛られずに応答できる点です。
1.家の中のどこでも応対
2階の書斎やベランダ、庭など、親機から離れた場所にいても、スマホが手元にあればすぐに応対できます。
2.外出先でも応対
Wi-Fiやモバイル回線に接続していれば、外出先からでも自宅への来訪者と通話ができます。映像で相手を確認できるため、急な来客や宅配便の配達にもリアルタイムで対応可能です。再配達を依頼したり、置き配をお願いしたりといった指示もその場でできるため、非常に便利です。
3.セキュリティ向上
玄関ドアの電気錠と連動させれば、外出先からスマホ操作で施錠・解錠することも可能です。また、不審な来訪者の映像を録画し、スマホで確認するといった防犯対策にも活用できます。
デメリットと注意点
便利なスマホ連動機能ですが、いくつかの注意点も存在します。まず、このシステムはインターネット接続が前提となるため、自宅のWi-Fi環境やスマホの電波状況によっては、音声や映像が途切れたり、遅延したりする可能性があります。
また、インターホンでの通話は、電話のように双方が同時に話せる「同時通話」ではなく、一方が話しているともう一方は聞く専門になる「交互通話(プレストーク)」が一般的です。そのため、電話のようなスムーズな会話は難しい場合があることを理解しておく必要があります。
導入にあたっては、既存のインターホンをスマホ連動対応の機種に交換する必要があります。
こちらの記事「スマホ連動の後付けインタホーンをマンションに最適な設置と活用法」も、参考にしてください。



機種によっては大掛かりな工事が必要になる場合もあるため、費用や設置方法については事前にしっかりと、確認することが大切です。
今人気の交換するならおすすめのインターホン


インターホンの交換を検討する際、どのメーカーのどの機種を選べばよいか迷う方も多いでしょう。ここでは、国内で高いシェアを誇り、機能性と信頼性で定評のある「パナソニック」「アイホン」を中心に、2025年現在で人気のあるおすすめのインターホン機種の特徴をご紹介します。
選ぶ際のポイント
機種を選ぶ際は、以下のポイントを比較検討するのがおすすめです。
1.モニターサイズと画質
画面が大きく高画質なほど、来訪者の顔や様子を鮮明に確認できます。
2.録画機能
留守中の来訪者を自動で録画できる機能は、防犯面で非常に重要です。動画で保存できるか、保存件数や期間も確認しましょう。
3.スマホ連携
外出先でも来客対応したい場合は、必須の機能です。
4.ワイヤレス子機
家の中の、どこでも応対したい場合に便利です。
5.工事の要否
DIYで取り付けたい場合は、工事不要のモデルを選びましょう。
おすすめの主要メーカーと人気シリーズ
| メーカー | 人気シリーズ | 主な特徴 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|
| パナソニック | 外でもドアホン (VL-SWZ700KFなど) | ・高精細な大画面モニター ・カラーナイトビジョン ・スマホや宅配ボックスと連携 ・デザイン性が高い | 最新機能と高画質を重視し、スマホ連携を活用したい方 |
| どこでもドアホン (VL-SWZ200KLなど) | ・ワイヤレス子機付き ・録画や夜間LED機能 ・コスパと機能のバランスが良い | 家中どこでも応対したい、価格と機能を両立したい方 | |
| 壁掛け式モデル (VL-SGZ30など) | ・配線工事不要 ・乾電池式で設置が簡単 ・賃貸やDIYに最適 | 賃貸住まいの方や、手軽に導入したい方 | |
| アイホン | ROCOワイド (KG-88など) | ・広角レンズで視野が広い ・操作がシンプル ・耐久性に優れる | 玄関全体を見渡したい方、直感的な操作を重視する方 |
| ワイヤレスモデル (WL-11など) | ・配線工事不要 ・スタイリッシュなデザイン ・親機は持ち運び可能 | デザインを重視し、工事なしで導入したい方 |
これらの情報は、あくまで一例です。インターホンは日々進化しており、新しいモデルが次々と登場します。



ご自宅の設置環境(電源直結式か、コンセント式か)や、家族構成、ライフスタイルに合わせて、最適な一台を見つけることが、満足度の高いインターホン交換につながります。
インターホンが聞こえないに関するよくある質問


インターホンが聞こえないという問題に関して、多くの方が抱く共通の疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。
- インターホンの交換は自分でできますか?
-
インターホンの電源方式によります。壁のコンセントにプラグを差し込む「電源コード式」や、乾電池で動く「乾電池式」のインターホンであれば、多くの場合、電気工事の資格は不要でご自身での交換が可能です。
しかし、壁の中から直接電源を取っている「電源直結式」の場合、交換作業には「電気工事士」の資格が必要です。無資格での作業は法律で禁止されており、大変危険ですので絶対にやめましょう。自宅のタイプが分からない場合は、プロの業者に相談するのが最も安全で確実です。
- 賃貸物件でインターホンが故障した場合、費用は誰が負担しますか?
-
賃貸物件のインターホンは、エアコンなどと同じく「設備」の一部と見なされます。そのため、入居者の故意や過失による故障でない限り、経年劣化などが原因の修理・交換費用は、基本的に大家さん(貸主)が負担するのが一般的です。
音が聞こえないなどの不具合に気づいたら、まずは管理会社や大家さんに連絡して状況を説明し、対応を相談してください。勝手に修理や交換を手配すると、費用を自己負担しなければならなくなる可能性があるので注意が必要です。
- サウンドモニターや音感センサーは、他の音にも反応しますか?
-
はい、反応する可能性が高いです。サウンドモニターや音感センサーは、特定の「ピンポーン」という音だけを聞き分けるのではなく、設定された音量以上の音や衝撃を感知して作動する仕組みの製品がほとんどです。
そのため、近くでの話し声やドアを閉める音、テレビの音など、インターホン以外の生活音にも反応してしまうことがあります。感度を調整できる製品もありますが、ある程度の誤作動は避けられない場合があることを理解した上で使用する必要があります。
- インターホンの寿命はどのくらいですか?
-
一般的に、インターホンの寿命は約10年~15年とされています。10年以上使用しているインターホンで、音が聞こえにくくなったり、映像が乱れたりといった不具合が出始めた場合は、部品の経年劣化が原因である可能性が高いです。部分的な修理が難しい場合も多いため、安全面や防犯性能の向上も考慮し、新しい機種への交換を検討する良いタイミングと言えるでしょう。



よくあるQ&Aも、参考にしてください。
まとめ:インターホンが別の部屋で聞こえない悩み
この記事では、インターホンが別の部屋で聞こえないという悩みについて、その原因から具体的な解決策までを多角的に解説しました。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。
- インターホンが聞こえない主な原因は、音の距離による減衰
- 壁や床などの建材が、音を遮断することも一因
- テレビや換気扇などの生活音が、呼び出し音をかき消す
- 高気密・高断熱住宅は、家の中の音も伝わりにくい
- 解決策として、工事不要のワイヤレスチャイム増設が手軽
- 音を感知して知らせる、サウンドモニターも有効な手段
- その場で応答できる、モニター子機の増設は利便性が高い
- 賃貸物件では、まず管理会社や大家さんに相談する
- 工事不要の製品を選べば、賃貸でも原状回復が可能
- 高齢者向けには、光や振動で知らせる製品が効果的
- 二階への後付けは、電源方式の確認が不可欠
- 電源直結式の工事は、電気工事士の資格が必要
- スマホ連動インターホンなら、外出先でも来客対応できる
- インターホン交換の際は、モニターサイズや録画機能を確認する
- 寿命の目安は、約10年〜15年とされている
【参考】
>>ポスト一体型のインターホン交換方法って?基礎知識や費用と注意点
>>インターホンとドアホンの違いとは?用途や特徴と失敗しない選び方
>>インターホンがならないようにするには?設定や静音対策の完全ガイド
>>古いタイプのインターホンは簡単に交換できる?費用や方法を徹底解説
>>インターホンを何回も鳴らす理由って?警察への通報や対処法を解説
>>インターホンのブレーカーが落ちる原因は?対処法と交換時の注意点
>>インターホンが両面テープで落ちるのはなぜ?原因と対策を徹底解説
>>インターホンで履歴が残らない時の対処法って?7つの原因と解決策