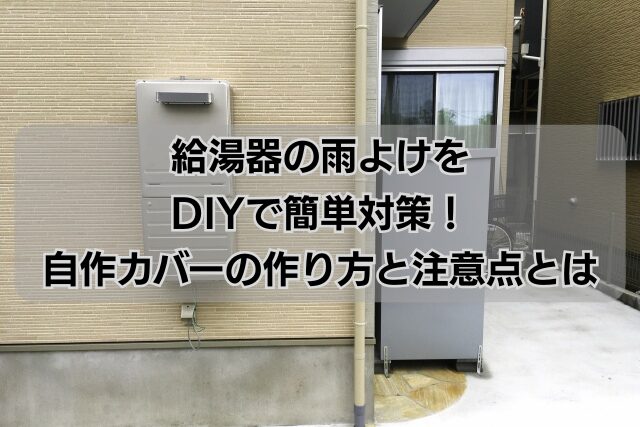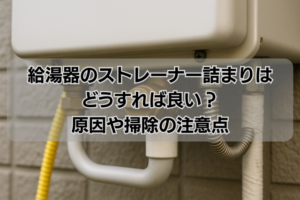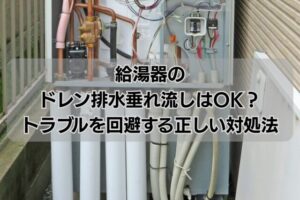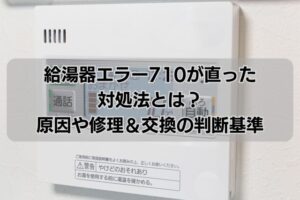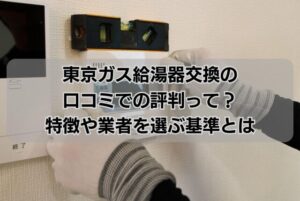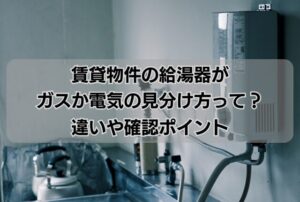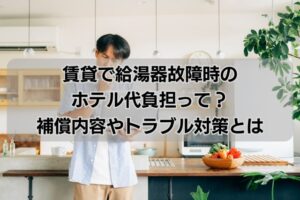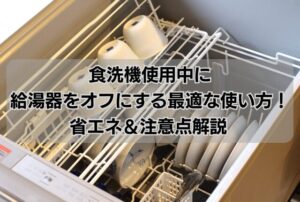給湯器の雨よけをDIYで作れるのかと疑問のあなたは、屋外に設置された給湯器への雨の影響を心配しているのではないでしょうか。実際、給湯器は風雨にさらされることで、思わぬトラブルを招くことがあります。
そこで本記事では、給湯器に雨よけが必要な理由、雨よけカバーをDIYで作る方法や注意点、また市販のカバーを使いたい方向けに、給湯器の雨よけはホームセンターで購入可能のかという情報をまとめています。
加えて、オンラインで購入する際の注意点や、万が一雨で給湯器が不調な時の対処法、雨が降ると給湯器で起こりうるエラーへの対応も詳しく解説。万が一の故障時にかかる修理費用相場も押さえています。
また、給湯器を交換する場合の補助金対象についてもご紹介しながら、費用を抑えたい方にとっても有益な情報まで網羅。信頼できる給湯器交換サービスの「東京ガスの機器交換」についても取り上げ、交換先選びに迷っている方にも役立つ内容となっています。
 ジロー
ジローDIY派の方も、既製品を検討中の方も、この記事を読めば給湯器の雨よけ対策がぐっと身近なものになるでしょう。
【記事のポイント】
1.雨から給湯器を守る、必要性とその理由
2.雨よけカバーを、DIYで安全に作る方法
3.ホームセンターやオンラインでの、資材購入のポイント
4.雨天時のエラーや、故障時の正しい対処法
給湯器の雨よけをDIYで作る方法と選び方


- 給湯器に雨よけが必要な理由とは?
- 雨よけカバーをDIYで作る方法
- 給湯器の雨よけはホームセンターで購入可能?
- オンラインで購入する際の注意点
- 雨で給湯器が不調な時の対処法
給湯器に雨よけが必要な理由とは?


給湯器には雨よけを設置したほうが安心です。特に屋外に設置されている場合、雨や湿気の影響を受けることで不具合が起こる可能性があるためです。
水に弱い繊細な構造を守る
これは、給湯器の内部に電子部品や燃焼系統など、水に弱い繊細な構造が多く含まれているからです。外装は耐水性を考慮して設計されていますが、強風を伴う雨や台風などでは、排気口やわずかな隙間から水分が入り込んでしまうケースもあります。
例えば、排気口はガス燃焼時に熱を逃がすための重要な部分であり、完全に密閉することはできません。そのため、強い雨が斜めや横から吹き込むと、ここから内部に湿気が入り、点火不良や安全装置の作動といったトラブルが発生することがあります。
古い機種の給湯器は注意が必要
一方で、近年の給湯器は防水性が高く、通常の雨で故障することは稀です。しかし、年数が経過した古い機種や、設置環境が悪い場合は話が別です。特に古いタイプの機器では経年劣化によってパッキンが劣化し、水が入り込みやすくなっていることもあるため、注意が必要です。
このように考えると、雨よけは給湯器のトラブルを未然に防ぐ「保険」のような役割を果たします。完全な防水対策とは言えなくても、リスクを大幅に減らすことができるため、設置を検討する価値は十分にあります。
ただし、雨よけを設置する際は「排気がこもらない構造」にすることが、大前提です。通気が確保されていないと、不完全燃焼や一酸化炭素の発生など、かえってリスクを招く恐れもあるからです。



安全を守るためにも、雨よけは正しく設置することが重要です。
雨よけカバーをDIYで作る方法
給湯器の雨よけカバーは、市販品を購入しなくてもDIYで作ることが可能です。しっかりとした設計と安全性を確保すれば、費用を抑えつつ給湯器を保護できます。
1.通気性と排気の逃げ道を確保
まず、DIYで作る場合に重要なのは「通気性」「排気の逃げ道」を、確保することです。給湯器は燃焼機器であるため、排気がこもる構造にしてしまうと不完全燃焼や火災などのリスクが高まります。したがって、カバーは「囲いすぎない」ことが大切です。
2.必要な材料と作り方
実際の作り方としては、以下の材料を使うと比較的簡単に作成できます。
- 軽量の波板(トタンやポリカーボネートなど)
- アルミ製のL字アングルやスチールフレーム
- ステンレス製のネジやボルト
- 屋外用の強力両面テープ(固定補助用)
- ドリルやのこぎりなどの工具
まず、給湯器の上部を覆うように、30〜50cmほどの隙間を空けて屋根のような形状で波板を設置します。強度を確保するためにL字アングルをフレームとして組み合わせ、給湯器の背面の壁に固定すると安定します。取り外しがしやすい構造にすると、メンテナンス時もスムーズです。
また、雨水が跳ね返るのを防ぐために、側面や下部にも一部覆いを加える設計も有効ですが、その際も空気の流れを妨げないように注意しましょう。
注意点として、木材は加工がしやすい反面、雨に弱いため、使用する場合は必ず防水処理を施してください。さらに、DIYで設置したものが風で飛ばないよう、しっかりと固定することが安全上の必須条件です。
このように工夫すれば、見た目もスッキリした雨よけカバーを自作できます。



ただし、DIYに自信がない場合や設置場所が高所である場合は、無理をせず業者に相談するのが安心です。
給湯器の雨よけはホームセンターで購入可能?


給湯器用の雨よけカバーは、多くのホームセンターで購入可能です。ただし、「給湯器専用カバー」という名称で販売されていることは少なく、実際には用途の近い汎用的な資材を組み合わせて対応するケースが一般的です。
ホームセンターで入手しやすい代表的な材料には、以下のようなものがあります。
- ポリカーボネート製や塩ビ製の波板
- 軽量な金属アングル(アルミやスチール)
- 木材(ただし防水加工が必要)
- 屋外用ビスやステンレスねじ
- 接着補助のための金具や両面テープ
例えば、波板を屋根代わりに使い、アングルとビスで壁面に固定することで簡易的な雨よけが作れます。給湯器のサイズや設置場所に応じて材料を選べば、比較的安価に必要なものをそろえることができます。
ただし、専用設計ではないため、自作にあたっては次のような注意点があります。
ひとつは、排気口の位置をしっかり確認し、排気の流れを遮らない構造にすることです。これが守られていないと、不完全燃焼の原因になります。もう一つは、強風や大雨でも外れにくいよう、十分な強度で固定することが求められます。
このように、ホームセンターで雨よけに使える資材は手に入りますが、それらをどう組み合わせて設置するかが安全性に直結します。



自作に不安がある場合は、設計段階から専門業者にアドバイスを求めると安心です。
オンラインで購入する際の注意点
給湯器の雨よけカバーをオンラインで購入する際は、いくつか注意しておきたいポイントがあります。見た目や価格だけで選ぶと、実際の設置に支障が出る場合があるからです。
1.サイズの適合性
まず、確認すべきは「サイズの適合性」です。給湯器のサイズや設置場所は家庭によって異なるため、製品の寸法と設置スペースが合っているかどうかを事前にチェックしておく必要があります。特に、排気口の位置や配線スペースが確保されているかも重要な確認事項です。
2.素材と耐候性
次に気をつけたいのが、「素材と耐候性」です。オンラインでは素材の質感や厚みが分かりにくいため、屋外使用に適した耐水・耐熱性能のある素材かどうか、商品説明をよく読みましょう。安価なものの中には、長持ちしない材質が使われているケースも見られます。
3.設置方法
さらに「設置方法」にも、注目してください。壁に固定するタイプなのか、据え置き型なのか、DIY初心者でも設置可能な仕様かなど、施工の難易度を事前に把握しておくことで、購入後のトラブルを回避できます。
4.詳細内容はレビュー数に注意
また、販売ページに詳細な説明が記載されていない商品や、レビューが極端に少ない場合は、避けたほうが無難です。実際に設置した人のレビューや写真があると、使用感や強度のイメージがしやすくなります。
5.返品や交換が可能かどうか
最後に、配送時の破損やサイズ違いなどに備えて、「返品や交換が可能かどうか」も必ず確認しておきましょう。特に大型商品は再配送や返送の手続きが煩雑になりやすいため、購入前に保証条件を確認することが重要です。
このように、オンライン購入は便利ですが、確認すべき情報を見落とすと無駄な出費や手間が発生します。



慎重に選ぶことで、満足のいく雨よけカバーを手に入れられるでしょう。
雨で給湯器が不調な時の対処法


雨の日に給湯器が動かなくなる場合、まずは落ち着いて基本的な確認から始めましょう。水が原因の一時的な不具合であれば、自力で解決できるケースもあります。
1.給湯器の再起動
最初に行うべきは、「給湯器の再起動」です。電源を一度オフにし、数分待ってから再びオンにしてみてください。湿気によるセンサー誤作動や一時的なエラーがリセットされ、正常に戻ることがあります。
2.ブレーカーやガス栓
続いて確認すべきは、「ブレーカーやガス栓」です。雨により給湯器内部で安全装置が作動し、電源が遮断されていることがあります。ブレーカーが落ちていないか、またガス栓がしっかり開いているかをチェックしてみましょう。特に、雷雨の影響で過電流が流れた場合は、ブレーカーが作動している可能性があります。
3.エラーコードの表示
さらに、リモコンにエラーコードが表示されているかも重要なヒントです。たとえば「111」などのエラーが出ている場合は、点火不良が起きている可能性が高く、湿気や水の侵入が関係していると考えられます。エラーコードに対応するマニュアルを確認するか、メーカーのサイトで内容を調べてみましょう。
4.給湯器が濡れた直後の操作に注意
ただし、外から見て異常がなくても、内部に水分が残っているケースもあります。その場合は、雨が止んで自然乾燥するのを待ってから再度電源を入れてください。給湯器が濡れた直後に操作すると、ショートや感電の恐れがあるため注意が必要です。
万が一、何を試しても回復しない場合や、給湯器本体に錆や破損が見られる場合は、専門業者に点検を依頼するのが安全です。内部の燃焼機器が劣化している可能性もあり、素人が無理に分解・修理を行うのは非常に危険です。
こうした一連の対処法を把握しておけば、雨の日でも慌てずに対応できるでしょう。



日頃から、給湯器周辺の通気や雨よけ対策をしておくことで、不調のリスクも大きく減らせます。
給湯器の雨よけをDIYしたけど不調の場合は?


- 雨が降ると給湯器で起こりうるエラー
- 故障してしまった場合の修理費用相場って
- 給湯器を交換する場合の補助金対象
- 給湯器交換なら安心の「東京ガスの機器交換」
- 給湯器雨よけをDIYする際によくある質問
雨が降ると給湯器で起こりうるエラー


雨の日に給湯器が突然エラーを起こすことは珍しくありません。特に、強風を伴う豪雨や台風などの悪天候時は、想定外の方向から雨水が侵入し、内部のセンサーや基板に影響を与えることがあります。
エラーコード111(点火不良)
主なエラーのひとつに、「エラーコード111(点火不良)」があります。これは、給湯器が点火できなかったときに表示されるエラーで、湿気によって内部の点火装置が正しく動作しなくなることが原因の一つです。特に古い機種では、パッキンの劣化やカバーのゆるみが水の侵入口になってしまうこともあります。
エラーコード112(追い焚き側の点火不良)
また、「エラーコード112(追い焚き側の点火不良)」も雨天時に発生しやすい症状のひとつです。こちらも湿気によって電子制御部品の動作が不安定になったときに表示されることがあり、突然お湯が使えなくなる原因となります。
エラー=故障ではない
こうしたエラーは、必ずしも給湯器の「故障」を意味するものではありません。一時的な湿気の影響や、雨風によって排気口に水が入り込んだだけで起こることもあります。実際、雨が止んで湿度が下がるとエラーが自動的に消えるケースも多く見られます。
ただし、何度も同じエラーが繰り返されるようであれば、給湯器内部の腐食やセンサーの不具合などが進行している可能性もあります。その場合は、リモコンでのリセットでは解決できないため、専門業者による点検を受けることが推奨されます。
エラーを未然に防ぐためには、給湯器の設置場所の見直しや雨よけの設置が有効です。



給湯器の周囲に湿気がこもりやすい環境である場合、換気や雨水対策を意識するだけでトラブルの発生頻度を大きく減らすことができます。
故障してしまった場合の修理費用相場って
給湯器が故障してしまった場合、修理費用は原因や部品の種類によって大きく変わります。目安としては、7,000円〜17,000円程度が一般的な相場ですが、状態によってはこれ以上かかるケースもあります。
| 不具合の種類 | 主な内容 | 修理費用の目安 |
|---|---|---|
| 軽度な不具合 | リモコンや基板、センサーなどの電装系 | 7,000円〜10,000円 |
| 燃焼系トラブル | 点火装置やバーナーの交換 | 15,000円前後〜 |
| 水回りの不具合 | バルブや水制御装置、内部清掃 | 約10,000円〜(内容により加算) |
軽度な不具合の場合
まず、軽度の不具合であれば電装系の修理(リモコンや基板交換など)で、7,000円〜10,000円程度で済むことが多いです。たとえば、センサーの誤作動やコードの接続不良などであれば、比較的短時間の作業で対応できるため、費用も抑えられます。
燃焼系トラブルの場合
一方で、燃焼系のトラブルになると少し高額になります。点火装置やバーナーの交換が必要になるケースでは、15,000円前後〜が目安です。さらに、交換する部品が特殊なものであったり、在庫が少ない古い機種であれば、部品の取り寄せ費用も加算されるため注意が必要です。
水回りの不具合
また、水回りの不具合(バルブや水制御装置など)についても、修理費用は10,000円前後が目安になります。こちらも状況によっては、部品交換のほかに本体の内部清掃などが必要になる場合があり、その分費用が上乗せされることもあります。
なお、ほとんどの業者では修理費とは別に出張費(2,000円〜5,000円程度)が発生します。この金額は地域や業者によって異なるため、事前に見積もりを取ることが重要です。
このように、故障の種類によって価格帯は異なりますが、修理費用が20,000円を超えるようであれば交換を検討するのも一つの選択肢です。特に、給湯器の使用年数が10年に近い場合や、同じ部位でトラブルを繰り返している場合は、修理を重ねるよりも長期的には交換のほうがコストを抑えられる可能性もあります。



安心して修理を依頼するためには、修理内容と費用の内訳を丁寧に説明してくれる業者を選ぶことがポイントです。
給湯器を交換する場合の補助金対象


給湯器を交換する際、条件を満たせば国の補助金制度を活用することができます。特に、環境性能に優れた「高効率給湯器」への交換であれば、家計の負担を軽減しつつ、省エネにもつながるメリットがあります。
給湯省エネ2025事業
現在注目されているのが、「給湯省エネ2025事業」による補助金です。これは、ヒートポンプ技術やハイブリッド方式を採用した給湯器を導入する家庭に対して、一定額が支給される制度です。
対象となる給湯器の種類には以下のようなものがあります。
- エコキュート(ヒートポンプ式給湯器)→ 最大130,000円/台
- ハイブリッド給湯器(ガス×電気の併用型)→ 最大150,000円/台
- 旧型の電気温水器や蓄熱暖房機を撤去した場合の加算補助→ 最大80,000円/台の加算
これらの補助を受けるには、政府が定めた性能基準を満たす製品を使用することが前提です。製品はあらかじめ補助対象として登録されており、登録製品でなければ補助を受けることはできません。
補助金を利用する方法と対象
加えて、補助金を利用するには「補助金申請の予約」「本申請」の、2ステップが必要です。申請期間は2025年4月14日から始まり、予約締切は11月14日、本申請は12月末までとなっています。予算には限りがあるため、早めの手続きが望ましいです。
なお、補助金の対象となるのは、個人住宅に設置される家庭用給湯器が基本です。事業用や業務用施設では対象外となることもあるため、詳細は公式の案内ページで確認しましょう。
このような制度を上手に活用することで、最新型の高性能給湯器をお得に導入できます。交換を検討している場合は、補助対象かどうかを事前に確認することが大切です。



補助金の対象機種は毎年見直されることもあるため、購入前に最新情報をチェックしておくと安心です。
給湯器交換なら安心の「東京ガスの機器交換」
給湯器の交換を検討しているなら、「東京ガスの機器交換サービス」は安心して利用できる選択肢のひとつです。信頼性の高い施工体制と、利便性の高いサービス内容が特徴です。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| オンライン見積もり | 写真と設置情報を送るだけで、最短即日に見積もりが届く |
| 住宅設備全般に対応 | 給湯器だけでなくトイレやコンロなども相談可能 |
| アフターサポート | 設置後の点検やトラブル対応までサポートが充実 |
オンラインでの見積もり依頼が可能
東京ガスでは、「オンラインでの見積もり依頼」が可能です。現地調査の前に、専用フォームから給湯器の写真や設置状況を送信するだけで、最短即日で見積もり結果が届きます。これにより、忙しい方でもスムーズに交換の検討が進められます。
住宅設備全般の相談も可能
また、対応している製品の種類が豊富で、ガス給湯器だけでなく、「トイレ・コンロ・レンジフード」など住宅設備全般の相談も可能です。給湯器だけでなく、水回りの設備を一括で見直したい方には便利なサービスです。
アフターサポートも充実
さらに、東京ガスでは施工品質にも力を入れています。設置工事は、法令を遵守した適正な基準に基づいて行われ、協力会社との連携により、「アフターサポート」も整っています。例えば、施工後の点検やトラブル時の対応もスムーズで、長期的な安心感があります。
価格面についても、キャンペーンや割引プランが適用されることがあり、他社と比べてもコストパフォーマンスが高いと感じるユーザーが多く見られます。補助金制度に関する相談や手続きのサポートにも対応しているため、不慣れな方でも安心です。
このように、東京ガスの機器交換は見積もりの手軽さ、施工の安心感、対応機種の豊富さの3拍子が揃っています。
「なんだか最近…給湯器の様子がおかしい…」
そんなお悩みありませんか?
- 給湯器を10年以上使っていて、調子が悪い…
- エラーが頻発する…
- しょっちゅう異音がして不安…
- お湯になるまで時間がかかる…
- イヤな悪臭がする…
東京ガスなら、ご自宅給湯器の写真を送るだけで、「最短当日無料見積もりが可能」です。
こちらの記事「東京ガス給湯器交換の口コミでの評判って?特徴や業者を選ぶ基準とは」では、東京ガス給湯器交換サービスの口コミやメリットデメリットなどを、徹底解説しましたので、参考にしてください♪



給湯器の交換を検討する際には、選択肢の一つとしてチェックしておく価値は十分にあるでしょう。
給湯器雨よけをDIYする際によくある質問
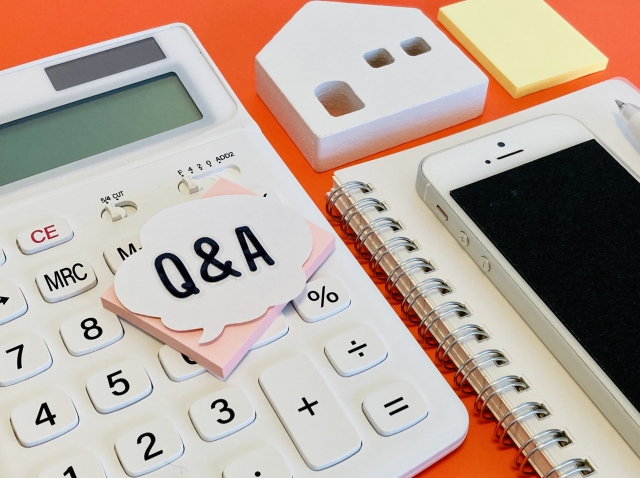
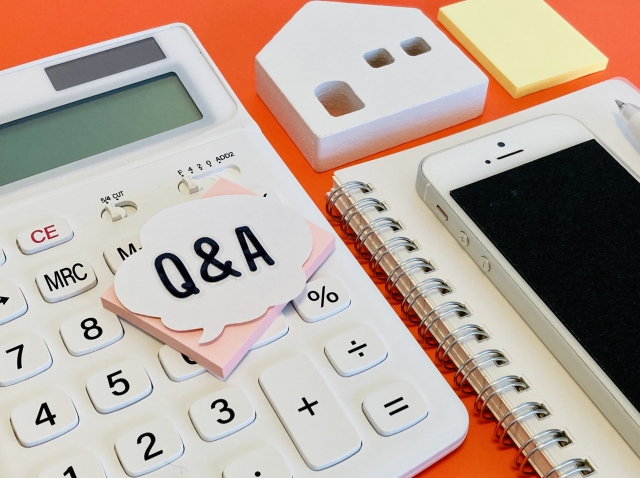
給湯器の雨よけをDIYで設置しようと考えたとき、多くの人が同じような疑問を持ちます。ここでは、よくある質問とその答えを紹介します。初めてDIYに挑戦する方にもわかりやすい内容を意識しています。
- 雨よけカバーは完全に給湯器を覆っても大丈夫ですか?
-
いいえ、給湯器を完全に覆うのは危険です。給湯器は燃焼時に排気が発生するため、通気性を確保しなければ不完全燃焼を起こす恐れがあります。囲いすぎず、排気口まわりには十分な空間を設けるようにしてください。
- 雨よけの素材は何を使えばいいですか?
-
屋外で使用するため、耐水性と耐久性に優れた素材を選ぶのが基本です。ポリカーボネート波板やトタン板、アルミパネルなどが人気ですが、木材を使う場合は防水処理を必ず施しましょう。長持ちさせるには、紫外線やサビにも強い素材を選ぶのがポイントです。
- 雨よけを壁に固定しても問題ありませんか?
-
可能ですが、壁の構造によっては注意が必要です。コンクリートやブロック壁であればアンカーを使ってしっかり固定できますが、外壁材によっては強度不足や雨漏りの原因になることもあります。不安な場合は専門業者に下地の確認を依頼しましょう。
- 雨よけのサイズはどのくらいにすればいいですか?
-
給湯器の上部に30〜50cm程度の余裕を持たせると、排気がこもりにくく安全です。横幅も雨が吹き込まないように本体より広めに設計しましょう。ただし、周囲に障害物がないかもあらかじめ確認しておくと安心です。
- DIYではなく既製品を使うべきですか?
-
DIYが苦手な方や、安全性に不安がある場合は既製品の使用も一つの方法です。ただし、給湯器メーカー純正の雨よけカバーはあまり流通しておらず、ほとんどが汎用タイプになります。設置後の排気確認など、安全面を十分に確認したうえで選びましょう。
このような質問を事前に確認しておくことで、DIYの失敗を防ぎ、給湯器を安全かつ長く使い続けることができます。



準備と下調べを丁寧に行うことが、DIY成功の秘訣です。
給湯器の雨よけをDIYで作るポイント総括
記事のポイントを、まとめます。
- 屋外設置の給湯器は、雨よけをつけることで不具合のリスクを減らせる
- 排気口からの浸水を防ぐには、構造に工夫が必要
- 古い給湯器はパッキンの劣化により、水が侵入しやすくなる
- 雨よけは完全密閉ではなく、通気性を確保した設計が必須
- 給湯器上部には、30〜50cmの隙間を確保して雨よけを設置する
- DIYでの雨よけは、波板やアルミアングルを使うと作りやすい
- 木材を使う場合は、必ず防水処理を行う必要がある
- 雨よけは強風対策として、しっかりと固定することが重要
- ホームセンターでは、波板や金具など必要資材を手に入れやすい
- 市販の雨よけは、「専用」と書かれていない汎用品が多い
- オンライン購入時は、サイズと排気口位置の確認が不可欠
- 安価な素材は、耐久性に難があるため慎重に選ぶ
- 雨の日の不調は、再起動やブレーカー確認で回復することがある
- 雨によるエラーは111や112が多く、湿気が原因となる
- 修理費が高額な場合は、交換と補助金制度の利用を検討すべき
【参考】
>>給湯器の水抜き栓を開けっ放しにした場合のリスクと対処法を徹底解説
>>給湯器のコンセントは抜いても大丈夫?安全性や節約効果など徹底解説
>>給湯器交換時に部屋が汚いとどうなる?片付けの必要性と対処法
>>給湯器を室内設置するデメリットって?騒音や安全面など注意点を解説
>>給湯器配管の凍結防止に必須!スポンジ保温材の役割と選び方とは
>>給湯器がうるさい!苦情を防ぐための異音の原因と具体的な対処法とは
>>給湯器無料点検訪問の実態とは?悪徳業者の手口と対策方法を解説
>>食洗機使用中に給湯器をオフにする最適な使い方!省エネ&注意点解説
>>賃貸で給湯器故障時のホテル代負担って?補償内容やトラブル対策とは
>>賃貸物件の給湯器がガスか電気の見分け方って?違いや確認ポイント
>>給湯器エラー710が直った対処法とは?原因や修理&交換の判断基準
>>給湯器のドレン排水垂れ流しはOK?トラブルを回避する正しい対処法
>>給湯器のスイッチカバーは100均にある?DIY術と注意点を解説
>>給湯器のストレーナー詰まりはどうすれば良い?原因や掃除の注意点