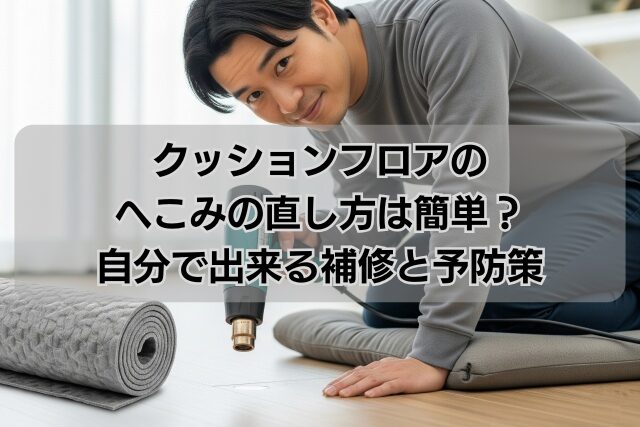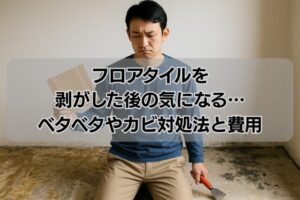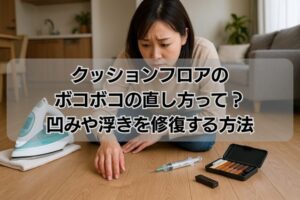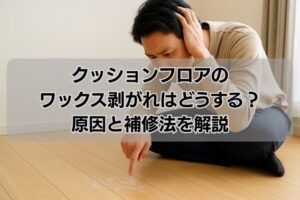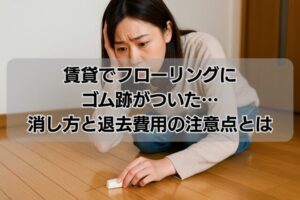「家具を動かしたときに現れる、クッションフロアのへこみ…」気が付くと、気分が落ち込みますよね。このへこみは自然に治るのか、それとも何か特別な対処法が必要なのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
特に賃貸住宅にお住まいの場合、退去時の原状回復は必要なのかという不安も、つきまといます。
この記事では、へこんでしまった時の対処法と適切な治し方から、今後のへこみを防ぐための対策のポイントまで、網羅的に解説します。100均で手に入るへこみ防止グッズの取り扱いはあるのか、効果的なへこみ防止マットの評判、そしておすすめの商品についても具体的にご紹介。
また、どうしても自分で直せない場合の選択肢として、クッションフロア補修をプロに依頼する場合の費用相場や、張り替えを検討する際に役立つおすすめのサービスについても、触れていきます。
 ジロー
ジローこの記事を読めば、クッションフロアのへこみに関するあらゆる悩みが、解消されるはずです。
【記事のポイント】
1.自分でできる、簡単なへこみの直し方
2.効果的なへこみ防止対策と、便利グッズ
3.賃貸物件における、原状回復義務の考え方
4.プロに補修や、張替えを依頼する際の費用相場
基本的なクッションフロアのへこみの直し方


- クッションフロアのへこみは自然に治る?
- へこんでしまった時の対処法と適切な治し方
- クッションフロアのへこみ対策のポイント
- 100均にへこみ防止グッズの取り扱いはある?
- クッションフロアのへこみ防止マットの評判
クッションフロアのへこみは自然に治る?


クッションフロアにできてしまったへこみは、ある程度の時間放置することで、自然に元に戻る可能性があります。なぜなら、クッションフロアは塩化ビニル層と裏打ちの間にスポンジ状の発泡層があり、この層が持つ復元力によって形状が回復するためです。
軽いへこみや、家具を置いていた期間が短い場合にできたへこみは、数日から数週間で目立たなくなることが多いです。家具を移動させた後、まずは何もせずに様子を見るのが最も手軽な方法と言えます。
ただし、へこみが元に戻る力には限界があります。
非常に重い家具を長期間置いていた場合や、一点に強い圧力が集中し続けていた場合、発泡層が完全につぶれてしまい、復元力が失われてしまいます。このような深いへこみは、残念ながら放置しているだけでは元通りになりません。



へこみが自然に治るかどうかは、圧力がかかっていた期間と重さに左右されるため、一概に「必ず治る」とは言えないのが実情です。
へこんでしまった時の対処法と適切な治し方


放置してもへこみが改善しない場合や、より早く修復したい場合には、熱を利用する方法が効果的です。ただし、クッションフロアは熱に弱い素材であるため、作業は慎重に行う必要があります。
蒸しタオルで温める
安全性が高く、初心者にもおすすめなのが蒸しタオルを使う方法です。水に濡らしたタオルを固く絞り、電子レンジで温めて蒸しタオルを作ります。これをへこんだ部分に当てて、しばらく置くだけです。
蒸しタオルの適度な熱と水分が発泡層の膨張を促し、へこみの改善を助けます。この方法はクッションフロアを傷めるリスクが低いため、安心して試すことができます。
ドライヤーで温める
プロも実践する方法として、ドライヤーの温風を当てるやり方があります。へこんだ部分から少し距離を離し、ドライヤーを低温設定にして1分ほど温風を当て続けます。蒸しタオルよりも継続的に熱を加えられるため、より効果が期待できます。
しかし、注意点として、絶対に高温設定にしたり、同じ場所に長時間温風を当て続けたりしないでください。
クッションフロアの表面が溶けたり、変色したりする原因となり、かえって状態を悪化させてしまいます。作業中は床の様子を常に確認しながら、慎重に進めることが大切です。
アイロンを使う(上級者向け)
アイロンは広い範囲のへこみに有効ですが、リスクが最も高い上級者向けの方法です。アイロンを低温に設定し、必ず濡らしたタオルをへこみとアイロンの間に挟んでください。直接アイロンを当てると、一瞬で床材が溶けてしまいます。



タオル越しに数秒ずつ、様子を見ながら慎重に熱を加えます。変色や溶解のリスクが非常に高いため、自信がない場合は避けた方が賢明です。
クッションフロアのへこみ対策のポイント


クッションフロアのへこみを未然に防ぐための最も重要なポイントは、床の一点にかかる圧力を分散させることです。家具の脚など、狭い面積に重さが集中することで発泡層がつぶれてしまうため、接触面積を広くすることが鍵となります。
具体的には、家具と床の間に何かを一枚挟むことで、荷重を面で支えるように工夫します。これにより、特定の場所だけが深く沈み込むのを防ぐことが可能です。
また、定期的に家具の位置を少しだけずらすことも、有効な対策の一つです。長期間同じ場所に圧力がかかり続けるのを避けることで、へこみが定着しにくくなります。
特にキャスター付きの椅子などは、知らないうちに同じ場所に負担をかけていることがあるため注意が必要です。



日頃から荷重を分散させる意識を持つことで、美しい床の状態を長く保つことができます。
100均にへこみ防止グッズの取り扱いはある?


クッションフロアのへこみ対策は、100円ショップで手に入るアイテムでも手軽に始めることができます。高価な専用品でなくても、工夫次第で十分に効果を発揮するグッズが見つかります。
代表的なものは、椅子の脚に履かせる「脚カバー」や、家具の脚の裏に貼り付ける「フェルトパッド」です。これらは本来、床の傷防止や移動時の音を軽減するための商品ですが、圧力を多少分散させる効果も期待できます。
特に布製の脚カバーは、汚れたら洗濯できるため衛生的です。
また、コルク製のコースターも活用できます。家具の脚の下に敷くことで、接触面積を広げ、荷重を分散させることが可能です。デザインも豊富なので、インテリアに合わせて選ぶ楽しみもあります。
ただし、これらのグッズはあくまで簡易的な対策です。
非常に重い家具や、脚の細い家具に対しては、効果が限定的である点は理解しておく必要があります。



手軽に始められる第一歩として、100均グッズを試してみるのは良い選択肢と言えます。
クッションフロアのへこみ防止マットの評判


より確実なへこみ防止対策を求めるなら、専用の「保護マット」の使用がおすすめです。特に、デスクチェアの下や冷蔵庫、ピアノといった重量物の下に敷くマットは高い評価を得ています。
チェアマット
キャスター付きの椅子によるへこみや傷を防ぐのに非常に効果的です。素材は主にポリカーボネート(PC)製と塩化ビニル(PVC)製があります。ポリカーボネート製は透明度が高く、床のデザインを損なわない点が人気です。耐久性にも優れていますが、価格は比較的高めです。
一方、PVC製は柔軟性があり、価格も手頃なため導入しやすいメリットがあります。ただし、長期間使用すると変色したり、素材の臭いが気になったりする場合があるという声も見られます。
冷蔵庫下マット
冷蔵庫は非常に重く、一度設置すると動かすことが少ないため、床のへこみや傷の原因になりやすい家電です。冷蔵庫下専用のマットは、高い耐荷重性を持つポリカーボネート製が多く、荷重を効果的に分散して床を守ります。また、地震の際の転倒防止や、水漏れから床を守る役割も果たすため、評判は非常に良好です。



これらのマットは、初期投資はかかるものの、床を長期間美しく保つ効果を考えると、費用対効果の高いアイテムだと言えるでしょう。
賃貸・プロに頼るクッションフロアのへこみの直し方


- 賃貸でクッションフロアのへこみに原状回復は必要?
- クッションフロア補修をプロに依頼する費用相場
- 張り替えをプロに依頼するならおすすめのサービス
- おすすめのクッションフロアへこみ防止商品
- クッションフロアのへこみでよくある質問
賃貸でクッションフロアのへこみに原状回復は必要?


賃貸物件にお住まいの方が最も気になるのが、退去時の原状回復義務についてです。結論から言うと、家具の設置によって生じた通常のへこみは、基本的に借主(入居者)が修繕費用を負担する必要はありません。
通常損耗
国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、家具の設置によるへこみや跡は「通常損耗」と位置づけられています。これは、普通に生活していれば自然に発生する範囲の損耗であり、その修繕費用は大家さん(貸主)が負担すべきものとされています。
耐用年数
また、クッションフロアには「耐用年数」という、考え方があります。ガイドラインによると、クッションフロアの耐用年数は6年です。これは、6年経つと建材としての価値がほぼゼロになるという考え方です。
したがって、6年以上住んだ物件であれば、たとえ借主の不注意で傷をつけてしまった場合でも、原状回復費用を請求されることは原則としてありません。
ただし、注意が必要なのは、家具を引きずってできた深いえぐれ傷や、キャスター付きの椅子で床を著しく損傷させた場合などです。
これらは通常の使用を超える「故意・過失」による損傷とみなされ、借主の負担となる可能性があります。



通常の生活範囲内でのへこみであれば、過度に心配する必要はないと言えるでしょう。
クッションフロア補修をプロに依頼する費用相場


自分で修復できない深いへこみや、広範囲の傷がついてしまった場合は、プロの業者に補修を依頼する選択肢があります。費用は、補修の方法や範囲によって大きく異なります。
| 補修の種類 | 費用相場(6畳の場合) | 特徴 |
|---|---|---|
| 部分補修 | 30,000円~60,000円 | 傷やへこみ部分のみを補修。費用は抑えられるが色味が合わない可能性あり。 |
| 重ね張り工法 | 20,000円~50,000円 | 既存の床の上から新しいものを張る。工期短く安価だが床が高くなる場合あり。 |
| 張替え工法 | 45,000円~70,000円 | 床材を全て張替え。仕上がりが最も綺麗だが費用と時間がかかる。 |
リビングのような広い空間の一部分だけを補修する場合は「部分補修」がコストを抑えられますが、トイレや洗面所など狭い空間であれば、全面を張り替えても費用に大きな差は出ないこともあります。



複数の業者から見積もりを取り、状況に合った最適な方法を選択することが大切です。
張り替えをプロに依頼するならおすすめのサービス


クッションフロアの張り替えを検討する際、どの業者に依頼すれば良いか迷うことも少なくありません。信頼できる業者を効率的に探すためには、リフォーム専門の一括見積もりサイトの利用が便利です。ここでは、代表的な2つのサービスをご紹介します。
リフォーム比較プロ
累計利用者数が30万人を超える実績のあるサービスです。厳格な審査基準をクリアした優良なリフォーム会社のみが加盟しており、評判の悪い業者は登録を削除する仕組みがあるため、安心して利用できます。
見積もり依頼だけでなく、無料でリフォームプランの提案を受けられる点や、「エクステリアプランナーによる無料診断」が受けられる点も大きな魅力です。専門家のアドバイスを受けながら、じっくりと業者を選びたい方に向いています。
こちらの記事「リフォーム比較プロの評判は本当?口コミの本音と失敗しない注意点」では、口コミやメリットデメリットなど他、評判や特徴を徹底解説しましたので、是非参考にしてください♪
リショップナビ
加盟業者数が多く、幅広い選択肢の中から比較検討できるのが特徴のサービスです。専門のコンシェルジュが電話で要望を丁寧にヒアリングし、条件に合った業者を最大5社まで厳選して紹介してくれます。
自分で業者を探す手間が省けるため、忙しい方でもスムーズに依頼を進めることが可能です。また、万が一工事で問題が発生した場合に備えた「安心リフォーム保証制度」が充実している点も、利用者にとっては心強いポイントと言えます。
こちらの記事「リショップナビの口コミが気になる…メリットデメリットや注意点とは」では、口コミやメリットデメリットなど他、評判や特徴を徹底解説しましたので、是非参考にしてください♪



ご自身の希望に見合う、サービスを検討してください。
おすすめのクッションフロアへこみ防止商品


へこみ防止に役立つ商品は、マット以外にもさまざまな種類があります。用途や家具に合わせて適切なものを選ぶことで、より効果的に床を保護できます。
ベニヤ板・アクリル板
食器棚や本棚など、ほとんど動かすことのない重量家具の下には、ベニヤ板やアクリル板を敷くのが最も効果的です。板が面となって荷重を支えるため、圧力が広範囲に分散され、へこみを強力に防ぎます。
ベニヤ板の見た目が気になる場合は、床の色に合わせたリメイクシートを貼ることで、インテリアに馴染ませることが可能です。
家具保護パッド・家具スライダー
テーブルやソファなど、時々動かす可能性がある家具には、脚の裏に貼り付けるタイプの保護パッドが便利です。フェルト製や樹脂製などさまざまな素材があります。
また、家具スライダーと呼ばれる製品は、滑りの良い素材でできており、床を保護しつつ家具の移動をスムーズにしてくれるため、掃除や模様替えの際に役立ちます。
ラグやカーペット
ダイニングテーブルと椅子の下など、特定のエリアをまとめて保護したい場合には、ラグやカーペットを敷くのが有効です。薄手のものでも一枚敷くだけで圧力が分散され、へこみ防止に繋がります。



さらに、防音効果やインテリアのアクセントとしての役割も果たしてくれるため、一石二鳥のアイテムです。
クッションフロアのへこみでよくある質問


ここでは、クッションフロアのへこみに関して、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- 放置してもドライヤーを当ててもへこみが直らない場合はどうすれば?
-
長期間の圧力で発泡層が完全につぶれてしまった場合、残念ながら自己修復は困難です。この場合、フローリング補修用のパテを使って物理的にへこみを埋める方法がありますが、色合わせなどが難しく、かえって目立ってしまう可能性もあります。
賃貸物件の場合は下手に手を加えず、退去時に管理会社に相談するのが賢明です。持ち家の場合は、前述の通りプロの業者に部分補修や張り替えを依頼することを検討しましょう。
- ゴム製の滑り止めマットを使っても大丈夫?
-
家具の滑り止めとしてゴム製のマットやシートを使用することは避けてください。ゴム製品に含まれる化学物質がクッションフロアの塩化ビニルと化学反応を起こし、床が黄色や茶色に変色してしまう「ゴム汚染」という現象を引き起こすことがあります。
この変色はクリーニングでは落とすことができず、張替えが必要になるケースがほとんどです。滑り止めを使用する場合は、ゴム製以外の素材(エラストマー樹脂など)を選ぶようにしましょう。
- へこみと傷の補修方法に違いはありますか?
-
へこみは床材の圧着によるものなので、熱を加えて復元を試みます。一方、表面がえぐれたり切れたりしている「傷」の場合は、熱を加えても治りません。浅い傷であれば、フローリング用の補修クレヨンや補修テープで目立たなくすることが可能です。
深い傷の場合は、部分的な張り替え(パッチワーク補修)が必要になります。



よくあるQ&Aも、参考にしてください。
【総括】クッションフロアのへこみの直し方
記事のポイントを、まとめます。
- クッションフロアのへこみは、復元力により自然に治ることがある
- 軽いへこみは数日から数週間で、元に戻る場合が多い
- 早く直したい場合は、ドライヤーや蒸しタオルの熱を利用する
- 熱を使う際は、変色や溶解に十分注意する
- アイロンの使用は、リスクが高く上級者向け
- へこみ防止の基本は、荷重を一点に集中させないこと
- 家具の下に板やマットを敷いて、圧力を分散させるのが効果的
- 100均の脚カバーやコースターでも、簡易的な対策は可能
- チェアマットや冷蔵庫下マットは、高い予防効果が期待できる
- 賃貸物件の通常のへこみは、原状回復義務の対象外(通常損耗)
- 家具の引きずりなど故意・過失による損傷は、借主負担となる
- クッションフロアの耐用年数は6年で、減価償却が考慮される
- 自分で直せない深いへこみは、プロへの依頼を検討する
- プロによる補修には、部分補修・重ね張り・張替えなどの方法がある
- 業者選びには、一括見積もりサイトの利用が便利
【参考】
>>フローリングのえぐれ傷補修は100均で可能?簡単DIY術をご紹介
>>クッションフロアのえぐれ補修は簡単?DIYで直す方法や予防策とは
>>カーペットを切るハサミの選び方って?上手に切るコツやおすすめ商品
>>フローリングのニス剥がれ補修のコツって?DIYやプロ依頼まで解説
>>フロアタイルのデメリット「カビ」を防ぐ!後悔しない対策法と注意点
>>カーペットを干す場所がない時の対処法って?室内での乾かし方のコツ
>>フローリングにカビキラーはNGって本当?正しい落とし方と予防策
>>クッションフロアのゴム汚染の落とし方って?原因や対処法のポイント
>>賃貸のフロアタイルはデメリットばかり?失敗しない選び方を徹底解説
>>カーペットの拭き掃除にウタマロクリーナーは最適?活用術や注意点
>>知らないと損!正しいフロアタイルの捨て方と処分のコツを徹底解説
>>フロアタイルの隙間を埋める方法って?DIYから業者依頼までを解説
>>カーペットの黄色い粉の原因と対処法が知りたい!掃除や予防策も解説
>>賃貸でフローリングにゴム跡がついた…消し方と退去費用の注意点とは
>>クッションフロアのワックス剥がれはどうする?原因と補修法を解説
>>カーペットの買い替え時期はいつなのか?寿命と交換サインを徹底解説
>>クッションフロアのボコボコの直し方って?凹みや浮きを修復する方法
>>フローリングで思いっきりゴロゴロしたい!痛くない床座生活を解説
>>フロアタイルを剥がした後の気になる…ベタベタやカビ対処法と費用
>>カーペットのへこみ防止は100均で可能?おすすめ対策とグッズとは